
「上智大学の推薦入学試験(公募制)ってどんな試験なんだろう?」
「合格率はどのくらいなんだろう?自分でも合格できるかな…」
「何から対策すればいいんだろう…」
上智大学における特別入試(総合型選抜試験)の一つとして実施されている、推薦入学試験(公募制)。
受験対策に取り組みたいものの大学の公式サイトに詳細が公開されていないため、どのような試験なのか、イメージが湧かない人は多いですよね。
推薦入学試験(公募制)では独自の選考基準が設けられており、一般選抜とは異なる対策が求められます。そのため、出願資格を満たせば誰でも挑戦できる一方、学力が高いだけでは合格できません。
上智大学の教育理念への深い理解を示し、自身の個性や高校での活動を効果的にアピールする必要があります。
そこで本記事では試験内容や倍率なども交え、上智大学の推薦入学試験(公募制)の特徴を解説します。合格者の体験談や対策法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※上智大学において「特別入試」は総合型選抜試験を指しています。
なお、上智大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。
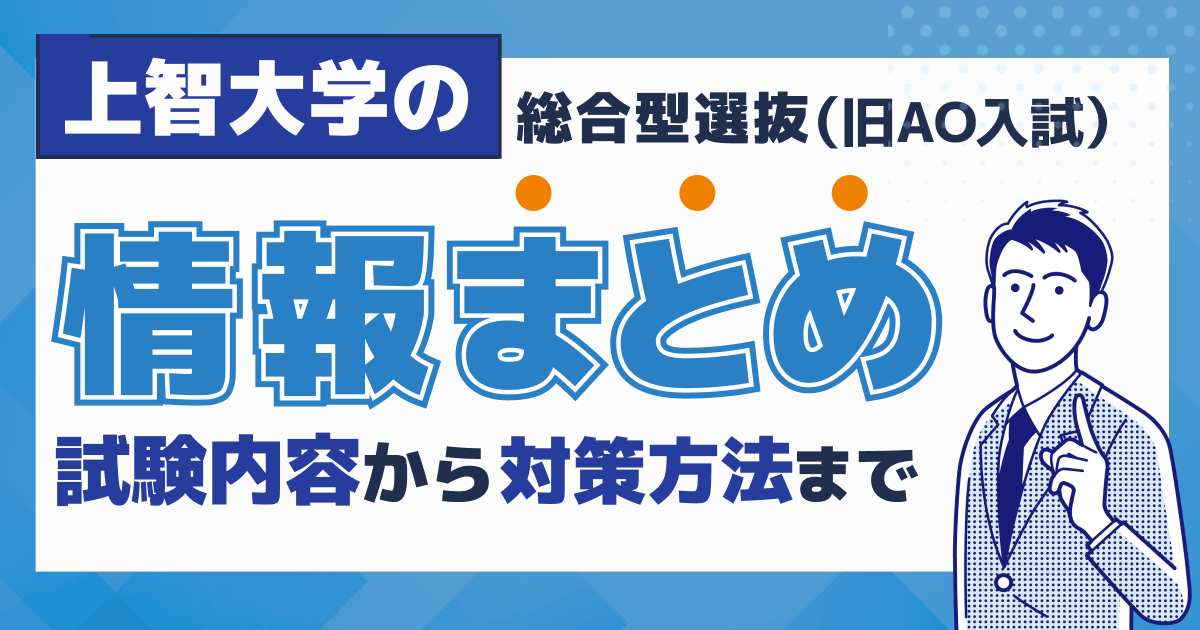
- 推薦入学試験(公募制)は特別入試(総合型選抜試験)の一つ
- 倍率は2.49倍
- 調査書・自己推薦書・特定課題・学科試問・面接で評価
なお、上智大学の総合型選抜試験の合格に向け「塾に通いたいけど、どこがいいのか選べない…」と悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。
かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。
効率よく上智大学に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。
\ 4つの質問に答えるだけ /
上智大学の推薦入学試験(公募制)とは?
上智大学の推薦入学試験(公募制)は、在籍している高校の校長から推薦を受けた生徒が出願できる入試制度です。
合否の判定は、提出書類だけで決まるわけではありません。各学科が課す個別テストや面接の結果などもあわせて、総合的に評価されます。
選考では、学力試験に加えて、受験生の能力や資質を多角的に評価するのが特徴です。具体的な選考方法として、主に以下の3つが挙げられます。
- 書類審査
- 学問試験
- 面接試験
なお、2026年度の試験日程は下表のとおりです。
| 出願期間 | ・Web出願:11月1日(土)~11月6日(木) ・書類出願(消印有効):11月7日(金) |
| 学問試験・面接 | 2025年11月29日(土) |
| 合格発表日 | 2025年12月11日(木) |
| 入学手続締切日 | 2026年1月9日(金) |
全学部で受験可能
上智大学の推薦入学試験(公募制)は、すべての学部・学科で実施されています。文系・理系を問わず、自分の学びたい分野へ出願できるのが大きな特徴です。
志望学科は任意に選択できますが、出願は1学科に限られます。また、同じ推薦入学試験である「指定校制」と併願することはできません。
そのため、指定校制と公募制どちらの制度でどの学科に出願するのか、慎重な判断が求められます。自分の興味や将来の目標を深く見つめ、最も学びたい学科を1つ選んで挑戦しましょう。
併願もできるが入学の確約が不可欠
合格後の入学を確約できることが、上智大学における推薦入学試験(公募制)の出願条件です。上智大学での志願学科を第一志望とし、出願後の辞退は原則として認められていません。
募集要項に「他大学との併願不可」という明確な記載はありません。しかし、入学を確約する必要があるため、実質的には専願の制度と理解しておくのが良いでしょう。
また、前述したとおり、同じ学内の推薦入学試験である「指定校制」と併願することもできないため、注意が必要です。
2025年度の倍率は2.49倍
2025年度の入学試験データによると、上智大学推薦入学試験(公募制)の倍率は2.49倍でした。これは全体の志願者1,294人に対し、合格者が519人だったことを示しており、約2.5人に1人が合格する計算です。
約2.5倍という数字は、難関私大の一般選抜に比べると低く見えるかもしれません。しかし、公募制推薦は出願資格を満たしたレベルの高い受験生のみが挑戦する試験です。
全国から高い評定平均で豊富な活動実績を持つ学生が集まるため、数字以上に厳しい競争となります。具体的には、高い外国語検定スコアや部活動での実績、ボランティア経験などが評価の対象です。単なる学力だけではない総合的な人間力が問われます。
安易に「倍率が低いから狙い目」と考えるのではなく、万全の準備で臨むことが不可欠です。
他の大学と総合型選抜の倍率を比較したい人は、下の記事も参考にしてください。
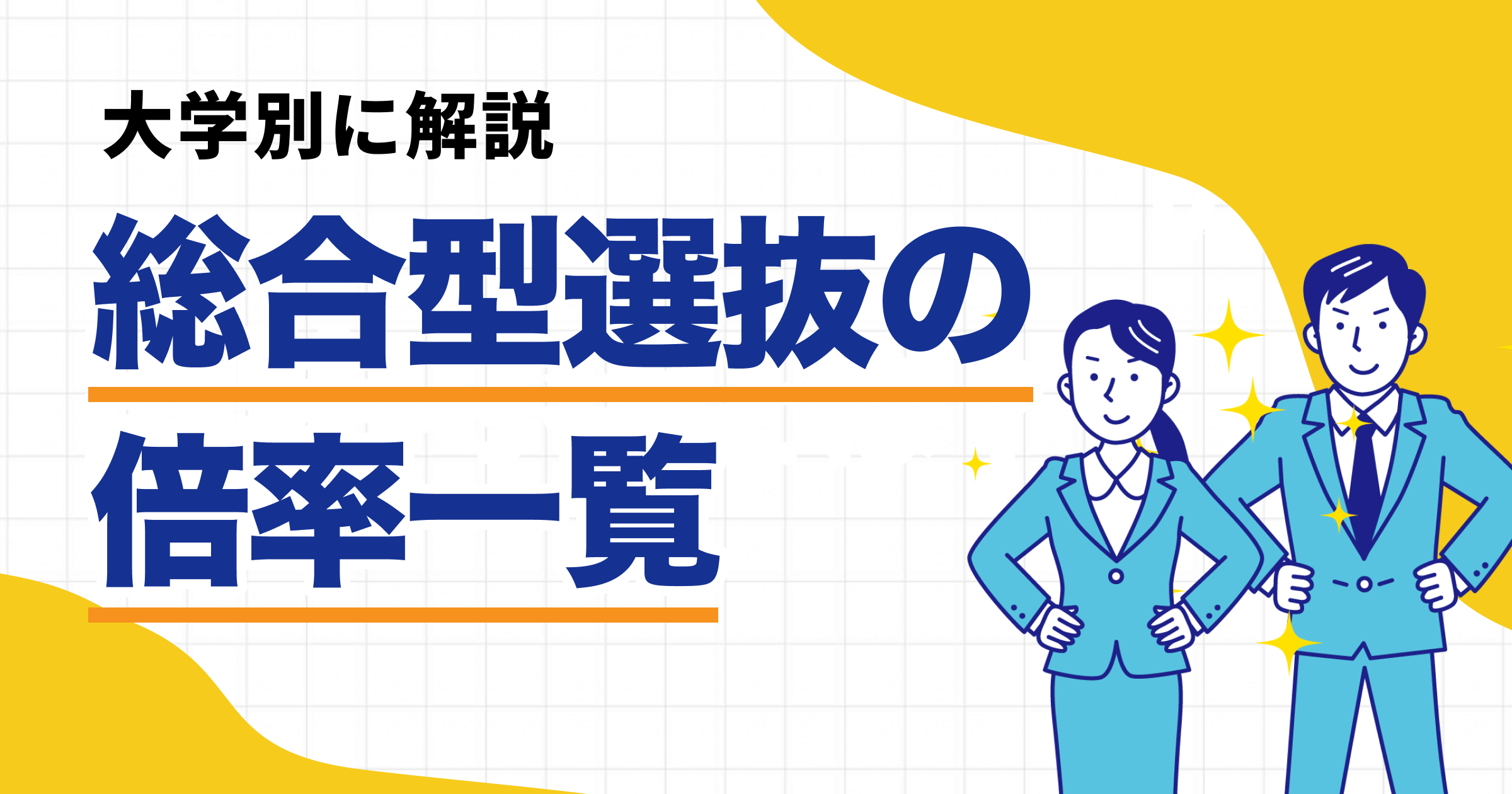
上智大学における推薦入学試験(公募制)の選考方法
上智大学の推薦入学試験(公募制)は、提出書類だけでなく、当日の筆記試験や面接を通して、受験生を多角的に評価するのが特徴です。ここからは、その具体的な選考方法3つを解説します。
選考は事前に提出する「書類審査」と、当日実施される「学科試問」「面接」に分かれます。それぞれの特徴を理解し、万全の対策で臨みましょう。
書類審査
書類審査では、主に「高等学校調査書」「自己推薦書」「レポート等特定課題」の3点が総合的に評価されます。出願者の情報を伝えるだけでなく、面接試験での質問の土台にもなる重要な書類です。
高校での学業成績や生活態度を示す客観的な資料です。特に全体の評定平均は、継続的な学習意欲と誠実さを証明する指標として重視されます。
なお、調査書に記載される評定について詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。
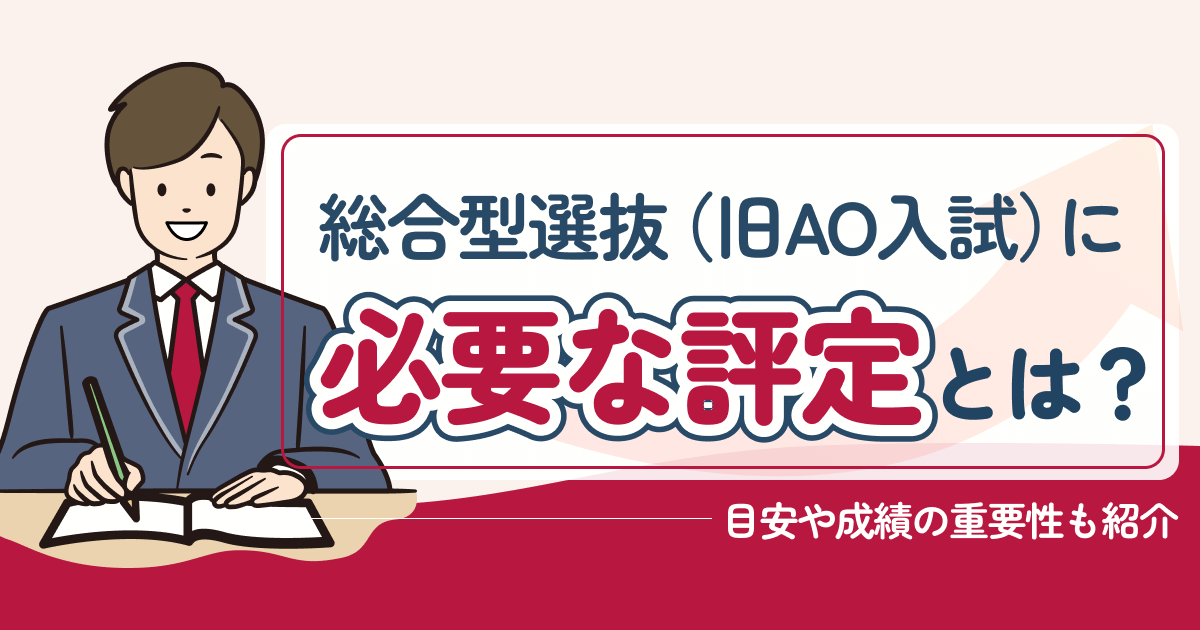
学科試問
学科試問は、志望する学部・学科の学問を学ぶ上で必要となる、基礎学力や思考力を測るための筆記試験です。その内容は学部・学科によって大きく異なり、それぞれに特化した対策が求められます。
文学部や法学部などの多くの文系学部では、「小論文」が課されます。小論文試験では、知識量ではなく、下記のポイントが総合的に評価される試験です。
- 与えられたテーマに対する深い理解力
- 論理的な思考力
- 自分の考えを的確に表現する文章力
外国語学部では各言語の運用能力が、経済学部では数学の基礎的理解力が問われます。より専門的な知識や技能が試される場合もあります。理工学部では物理・化学・生物から2科目を選択して解答する形式が取られています。
学科試問は学部・学科との相性を見る重要な選考です。必ず大学の公式サイトで志望学科の試験内容と過去問を確認し、傾向を掴んだ上で十分な演習を重ねておきましょう。
面接試験
面接は、選考の最終段階として、受験生と面接官である大学教員との対話形式で行われます。提出した自己推薦書などの書類をもとに、質疑応答が進められます。
面接では、下記のような点が総合的に評価されます。
- 志望理由の明確さや熱意
- 志願学部・学部への理解度
- コミュニケーション能力
- 人柄
- 大学入学後と卒業後の将来の可能性
多くの学部では日本語で面接が行われます。国際教養学部の面接は、すべて英語で実施されるため英語での準備も必要です。
自分の考えを明確に伝えられるよう、事前に伝えたいポイントを整理しておくことが重要です。丸暗記した回答ではなく、自然な会話を心がけ、模擬面接を繰り返し練習して本番に臨みましょう。
上智大学の推薦入学試験(公募制)におけるアドミッションポリシー
アドミッションポリシーとは、大学が「どのような学生に入学してほしいか」を具体的に示した方針です。推薦入学試験(公募制)は、個性や資質を評価する入試制度のため、アドミッションポリシーに合致していることが重視されます。
上智大学では、特に下記の4つの人物像を求めています。自己推薦書や面接でアピールする上で、指針となります。
| キリスト教ヒューマニズムの実践 | 他者や社会に奉仕する中で、自らの人格を高めていこうとすること。 |
| 他者に仕えるリーダーシップ | ”For Others, With Others”の精神で、他者と共に生き、社会に貢献する意欲があること。 |
| グローバルな能力 | 世界が抱える問題に関心を持ち、多様な文化の架け橋となれること。 |
| 専門分野を学ぶ意欲 | 幅広い教養と、専攻する学問分野の専門知識を修得する強い意欲があること。 |
自己推薦書やレポートを作成する際は、自身の経験や活動がこれらのどの項目に結びつくかを考え、具体的に記述することが合格への近道です。大学が求める人物像と自分が一致していることを、説得力を持って伝えましょう。
参考:アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)|上智大学 入試情報
総合型選抜におけるアドミッションポリシーの重要性をもっと詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。自身の結びつきをアピールするコツも紹介しています。
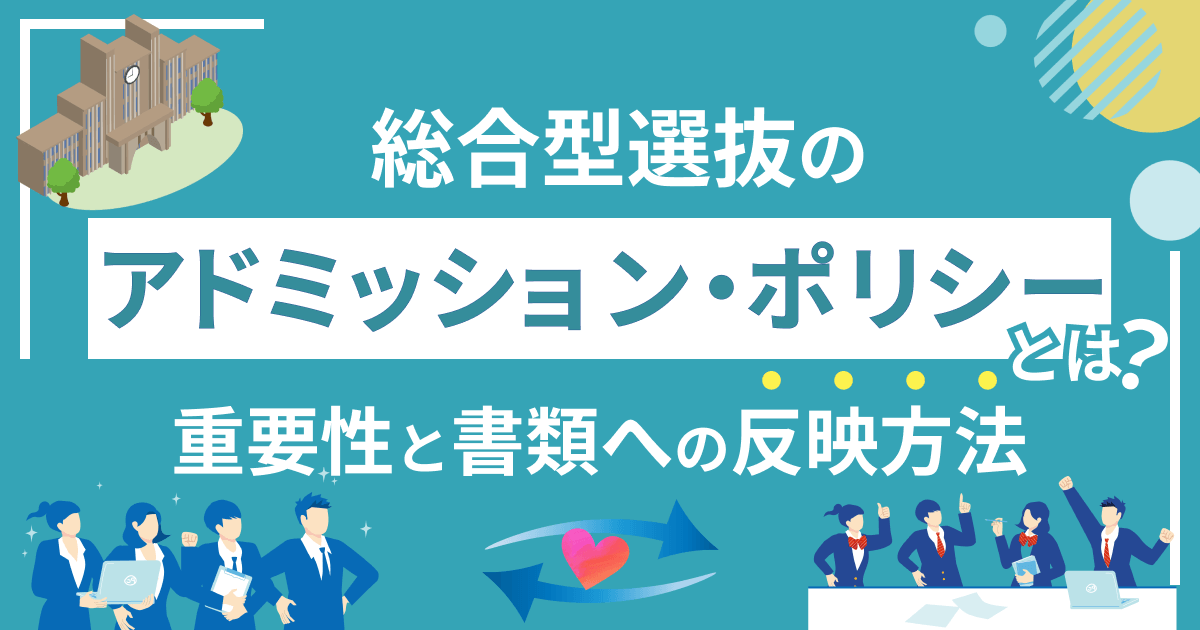
上智大学における推薦入学試験(公募制)の合格体験談
ここからは合格のコツも交え、上智大学の総合型選抜に合格した人の体験談を紹介します。
文学部に合格したK・Mさん
■上智大学を目指した理由、学部学科を選んだ理由
引用:特別入試で合格|上智大学 入試情報
自分のやりたいことが全てできるのが上智の文学部史学科だったからです。 私は大学を選ぶにあたり以下の5つの条件で探していました。 ①西洋史が学べること、②舞台芸術系の授業があること、③他学部他学科履修がしやすいこと、④教員免許が取れること(中学社会、高校地歴、高校公民)、⑤ロシア語が学べることです。 オープンキャンパスで様々な説明を聞いたり、実際に先生方や学生さんのお話を聞いていくうちに上智が全ての条件を満たすと気づき、第1志望校としました。また、オープンキャンパスで初めて上智に足を踏み入れた瞬間、「私ここに行きたい、私が求めているものが全てある」と雷に打たれたように直感したのもきっかけです。
■受験期を振り返って
【前期】コロナ禍で学校が2ヶ月休みになったので学校の課題をこなしつつ、一般入試の対策を中心に行っていました。 前期の途中からは公募の自己推薦書の内容を少しずつ考え始めました。
【夏休み】午前中〜15時頃までは一般入試対策(共通テストや赤本を解く)、15時以降は公募の書類準備や課題図書を読み進める、夜は暗記物の勉強をルーティンとしていました。公募の過去問も夏休みに3年分解きました。また、夏休み中に英検準1級を取得しました。(コロナで試験がずれ込んだため夏休み中になりました。)
【直前期】
9月:自己推薦書を書き上げる
10月:公募過去問2周目、面接練習も開始(週1くらい)
11月:公募過去問3周目
直前期も一般入試対策を行っており、平日は苦手つぶし、土日は過去問演習を行っていました。高2の秋から受験終了まで1日1題以上、現代文・古文・漢文・英語の長文を解くのをルーティンとしていました!
■おすすめの勉強方法
毎日全科目に触れることが大切です。共通テストのみ科目(理科基礎など)は毎日でなくても大丈夫ですが、英語・国語・世界史or日本史は毎日触れるべきです。 知識はアウトプットすることで身につくので、演習を通して身につけるようにしてください。また、過去問演習を早めに始めましょう。 「実力がないのにやっても…」と思うかもしれませんが、初めて過去問演習をする時は点数が取れなくて大丈夫です。 敵を知る、身につけるべき力を知る、弱点を知るということを目的に行い、そこで見つけたものを復習で身につければよいのです。 恐れずに過去問演習をやりましょう!
■面接の対策について
経験者の話を聞いたり、面接で聞かれる王道の質問にどう答えるかを考えました。また、面接では教授(大学)と学生のマッチ度が図られると考えていたので、自分の希望がいかに上智とマッチしているかを論理的に伝えられるように練習しました。面接練習は社会科の先生と上智出身の先生にお願いして、面接を通しでやってもらったり、自分の考えを論理的に伝える練習をしてもらいました。面接は発表ではなく会話なので、事前に回答を準備してそれをペラペラ喋るのはふさわしくありません。だからといってノープランで臨むのは違うので、言いたいキーワードをいくつかピックアップしておくという心づもりでいるとよいと思います。
K・Mさんの体験談からわかる、合格のコツは次の4点です。
- 大学選びの明確な条件を持ち、オープンキャンパスで徹底的に確認する
- 一般選抜と推薦対策を両立させ、時期ごとにやるべきことを決めておく
- 過去問は「敵を知る」ために早めに着手し、繰り返し解く
- 面接は「大学とのマッチ度」を伝える場と捉え、丸暗記ではなくキーワードで話す練習をする
まずは「なぜ上智大学なのか」を自分の中で明確に言語化することが大切です。その上で、一般選抜の勉強と両立させます。推薦対策のスケジュールを立てて早期から実行に移すという計画的な姿勢が合格に繋がります。
文学部に合格したS・Kさん
■上智大学を目指した理由、学部学科を選んだ理由
引用:特別入試で合格|上智大学 入試情報
オープンキャンパスの際、英語をはじめ多くの言語が上智大のキャンパスにはあふれているというお話を伺いました。そのグローバルな環境に憧れを抱き上智大学を目指すようになりました。また、高校で英語を学ぶ楽しさに気づき、大学でももっと深く学んでいきたいと考えていました。ただ、英語の何を学びたいのか、また、英語を用いて何をしたいのかがはっきりしていませんでした。そこで、英文学、言語学、英語教育といった様々な角度から英語にアプローチできる文学部英文学科を志望しました。
■受験期を振り返って
【前期】各教科の基礎学習をしていました。夏休みは、応用問題や過去問題を解きたいと考えていたのと、推薦対策もしたかったため、基礎は早めに固めようと思っていました。
【夏休み】応用問題と過去問題を解いていました。また、同時並行で推薦入試対策も進めていました。志望理由書とレポート課題の2つに取り組んでいました。しかし、推薦対策に思った以上に時間がかかってしまい、夏休み後半は一般対策がおろそかになりがちに。それでも、問題を全く解かない日は作らないようにと心がけていました。
【直前期】推薦入試当日で筆記試験のある英語の受験勉強、面接対策をしていました。推薦入試の学科試問は、一般選抜の試験問題と傾向が異なっていたため、一般選抜の勉強とは別に、推薦入試対策のための英語の勉強をしていました。面接対策は、開始時期が遅れてしまった焦りもあり、毎日のように先生に練習をお願いしていました。また、面接対策用のノートを1冊作り、面接で伝えたいことをまとめたり、先生からのアドバイスをメモするようにしていました。
■勉強の息抜き・気分転換
勉強するときは、集中するため塾の自習室に行っていました。疲れてしまったときは、気分転換に一度塾の外に出ておやつを買ったり、散歩をしたりしていました。外気にあたることでリフレッシュできていました。
■面接の対策について
面接用の参考書を1冊購入し、それに記載されていた質問は答えられるように準備していました。ただ、それだけでは不十分なので、実際に先生に面接練習を手伝っていただいていました。また、英文学科は面接が日本語と英語の両方で行われるため、日本語で言えることは英語でも言えるように、また、即興でも英語で内容を伝えられるように練習をしていました。
S・Kさんの体験談からわかる、合格のコツは次の4点です。
- 推薦対策は想像以上に時間がかかることを念頭に置き、早めに基礎を固めておく
- 推薦入試専用の対策ノートを作り、考えやアドバイスを一元化する
- 学科試問は一般選抜と傾向が違うため、専用の対策を行う
- 英語面接がある場合は、日本語で言いたいことを英語でも表現できるよう練習を重ねる
推薦入試の特殊性を理解し、特化した対策を行います。「推薦対策は時間がかかる」と意識しましょう。対策ノートで情報を一元化するなど、工夫をしながら効率的に準備を進めることが、合格への近道です。
【試験別】上智大学の推薦入学試験(公募制)に合格する対策法
ここからは前述した試験別で、推薦入学試験(公募制)に合格する対策法を解説します。
それぞれの評価ポイントを理解し、合格に向けた準備を進めましょう。
調査書
調査書は、高校3年間の学校生活を大学に伝えるための書類です。学習成績、特別活動の記録、出欠状況などが記載されます。
重要な項目は「評定平均」です。評定平均は短期の勉強では決して上がりません。高校1年からの日々の授業や提出物への取り組みの積み重ねが必要です。そして、定期試験での成果が高い評価として現れます。
欠席日数が少ないことは、真面目さや自己管理能力の証明です。部活動や委員会、ボランティアなどの課外活動も、主体性や協調性をアピールする上で有利に働きます。
総合型選抜における調査書の評価ポイントや対策法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。
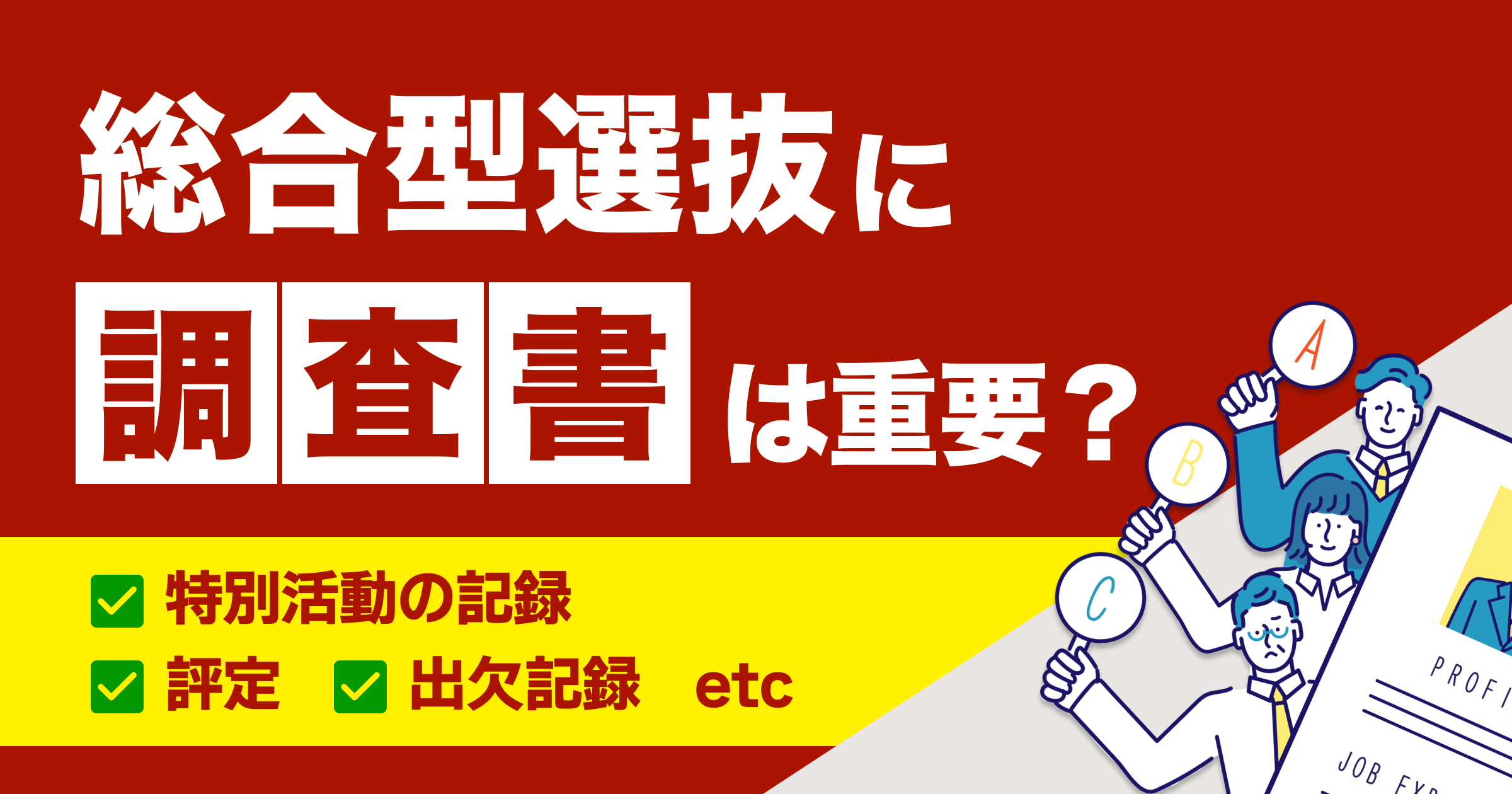
自己推薦書
自己推薦書は、自分の強みや熱意をアピールするための書類です。下記の点をアピールしましょう。
- 志望理由:なぜ上智大学なのか
- 経験:高校で何を頑張ったか
- 将来のビジョン:入学後にどう成長したいか
重要なのは、上智大学の教育理念(アドミッションポリシー)と自分の経験を具体的に結びつけることです。大学が求める人物像と自分が合致していることを、説得力のあるエピソードを交えて論理的に構成しましょう。
大学所定のA4用紙1枚以内であれば、手書き・PC入力のどちらでも作成できます。フォントの種類や文字サイズ、行数にも指定はありません。ただし、自由度が高いからこそ、読みやすさへの配慮が問われます。
小さすぎる文字や奇抜なフォントは避け、誰が読んでも内容がスムーズに頭に入るような、丁寧なレイアウトを心掛けてください。
参考:推薦入学試験(公募制)に関するFAQ|上智大学 入試情報
レポート等特定課題
レポート等特定課題は、出願時に提出が求められる課題です。学科に関連するテーマが与えられ、専門分野への関心や思考力が評価されます。
レポート等特定課題では、主に下記の力が試されます。
- 専門分野への関心と理解度
- 情報を整理・分析する能力
- 自分の考えを論理的に説明する文章力
まずは大学公式サイトの案内に従い、過去3年分の入試問題をEメールで取り寄せ、出題傾向を掴みましょう。
書式は入学試験要項の指示以外に細かな指定はなく、基本的には自分で判断して作成します。参考文献も、要項に特段の記載がなければ文字数には含みません。
原稿用紙を使用する場合、縦書き・横書きなどの指定を守れば市販のもので問題ありません。自筆で作成する際は、消えないように黒のボールペンで記入しましょう。完成したレポートは、左上をホチキス留めして提出します。
完成度を高めるために、高校の先生や塾の講師など第三者に読んでもらい、客観的な視点で添削してもらうのもおすすめです。
参考:推薦入学試験(公募制)|上智大学 入試情報、推薦入学試験(公募制)に関するFAQ|上智大学 入試情報
総合型選抜のレポート課題についてより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。
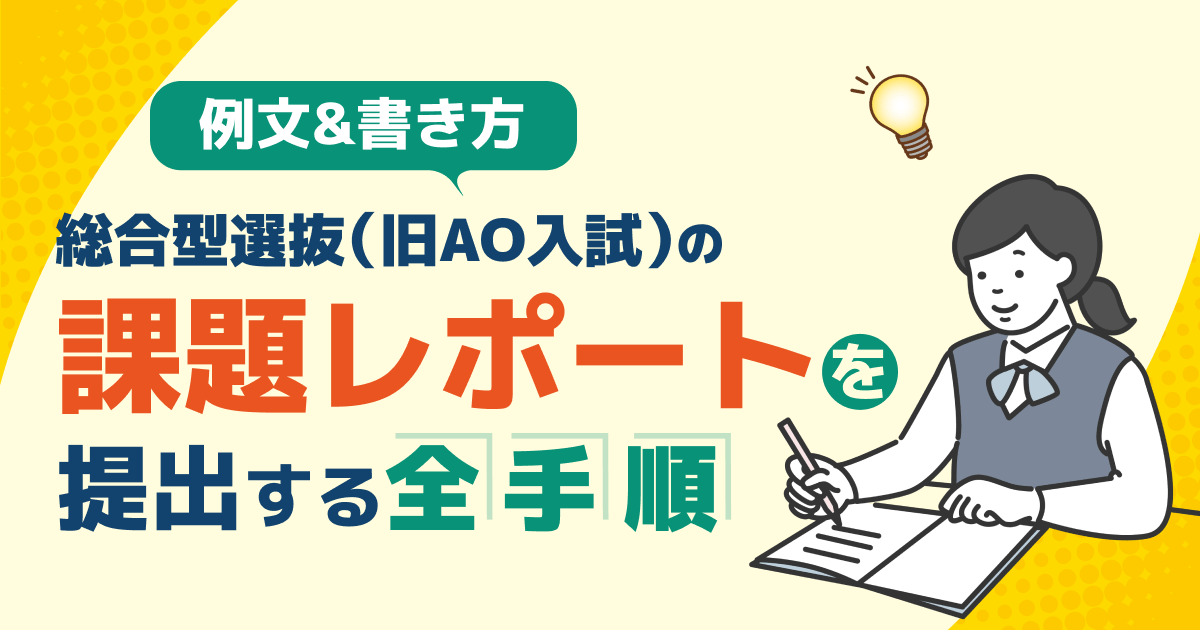
学科試問
学科試問は、主に小論文・論述形式で実施されます。志望する学問分野への深い理解度と思考力、表現力が一貫して問われます。知識の暗記ではなく、自分の考えを論理的に構築する力が試される試験です。
合格レベルに達するには、時間を計って書き切る訓練が不可欠です。試験時間である60分または90分で構成を考え、文章を完成させる練習を、週に1〜2本を目安に繰り返しましょう。
その際、基本となる「型」に沿って書くことを意識すると、論理的な文章が作りやすくなります。特に指定がない限り、下記の構成を心掛けましょう。
- 序論:問題提起をする
- 本論:根拠や具体例を挙げて多角的に論じる
- 結論:自分の考えを明確に述べる
書き上げた小論文は、学校の先生や塾の講師など、第三者に添削してもらいましょう。客観的な視点で指摘を受けることで、自分では気づけない矛盾点が修正でき改善点が明確になります。
面接
面接は、提出した書類をもとに、志望理由や高校生活での経験について質問される対話形式の試験です。書類だけではわからない、人柄や学習意欲を直接伝える場となります。
当日に向けて、自分の長所や学びたいことなど、面接官に伝えたいポイントを事前に整理しておきましょう。ポイントを整理することで、落ちついて自信を持って受け答えできるようになります。
国際教養学部で実施される英語での面接では、流暢さよりも、自分の意思を伝えようと努力する姿勢が重視されます。高校の授業で習得したレベルの英語で、積極的にコミュニケーションを図りましょう。
模擬面接などを活用し、本番の雰囲気に慣れておくことも大切です。
なお、面接の終了時刻は、当日の受験者数や面接順によって変わるため、事前に知ることはできません。
遠方からの受験などで帰宅時間に制約がある場合は、あらかじめ復路の交通機関を遅めの便で予約しておきましょう。当日の筆記試験終了後、控室のスタッフに事情を伝えれば、可能な範囲で配慮してもらえます。
参考:推薦入学試験(公募制)|上智大学 入試情報、推薦入学試験(公募制)に関するFAQ|上智大学 入試情報
総合型選抜における面接対策や質問例をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。
面接試験-1.png)
まとめ
本記事では、上智大学の推薦入学試験(公募制)について、特徴から対策までを解説しました。
上智大学の推薦入学試験(公募制)は、大学の理念に共感し、自らの個性や経験をアピールできるかが問われます。書類・学科試問・面接と、選考の各段階で求められる力を正しく理解し、計画的に準備を進めることが欠かせません。
この記事で得た知識を最大限に活用し、万全の対策で合格を掴み取りましょう。
こちらの記事もおすすめ
-scaled.png)
入学試験-scaled.png)
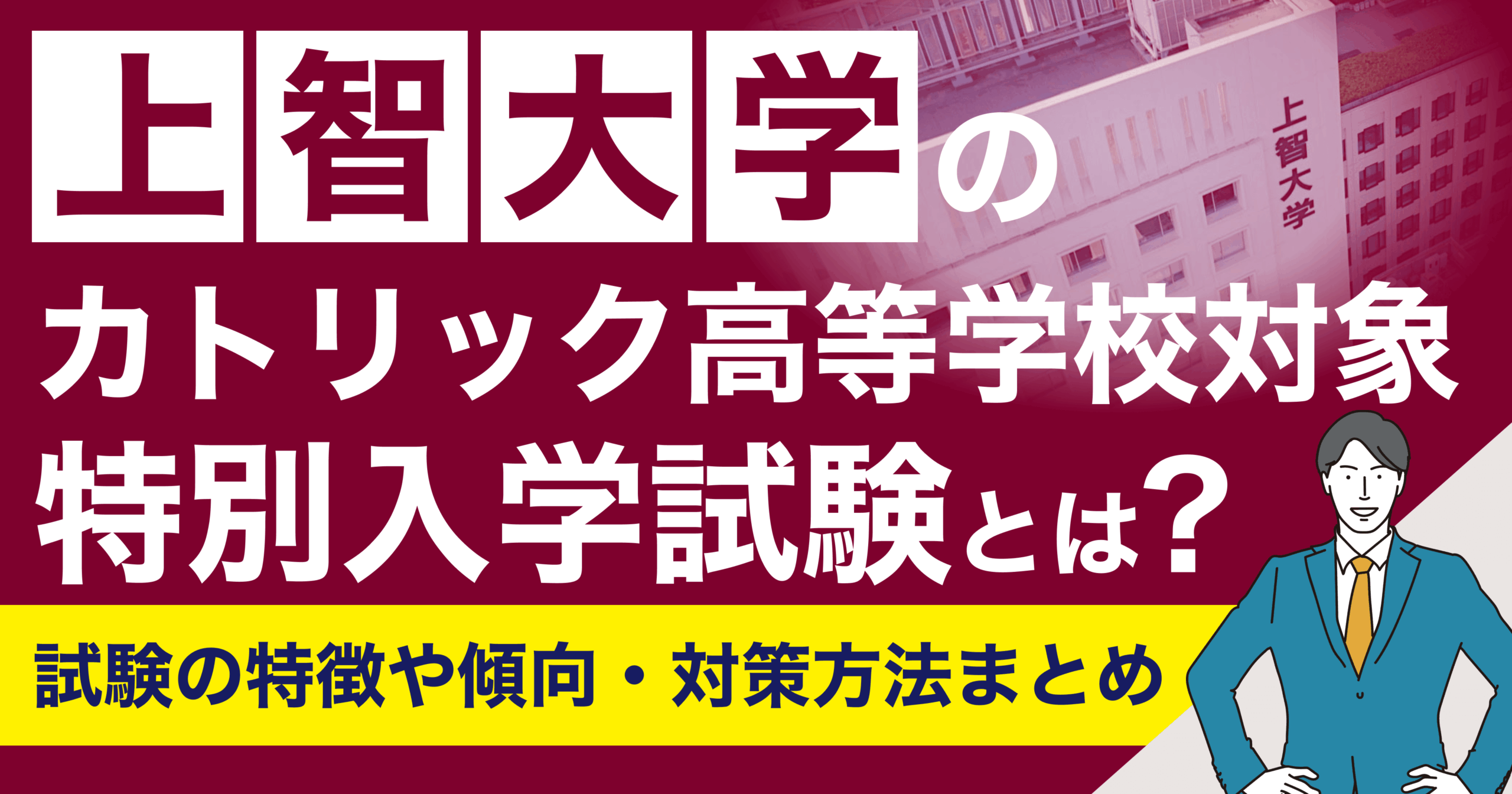

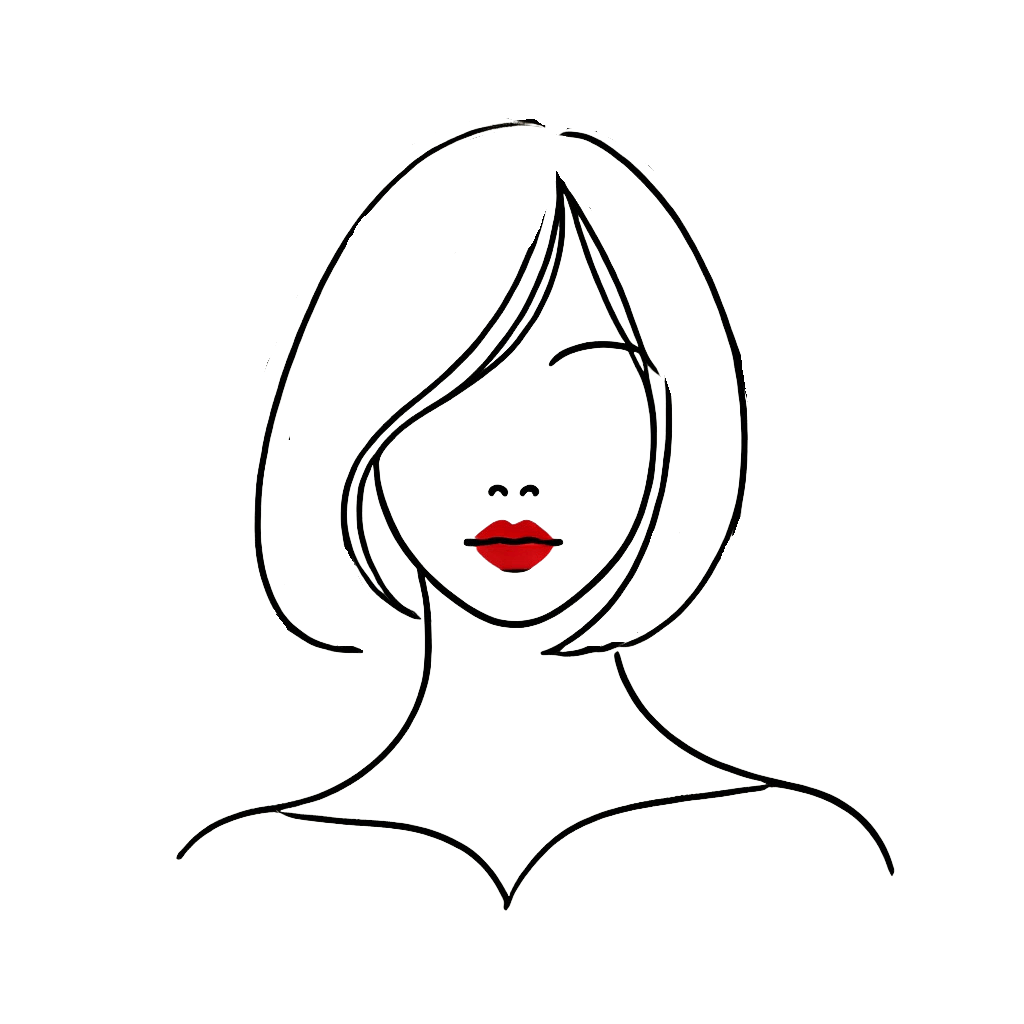
-scaled.png)