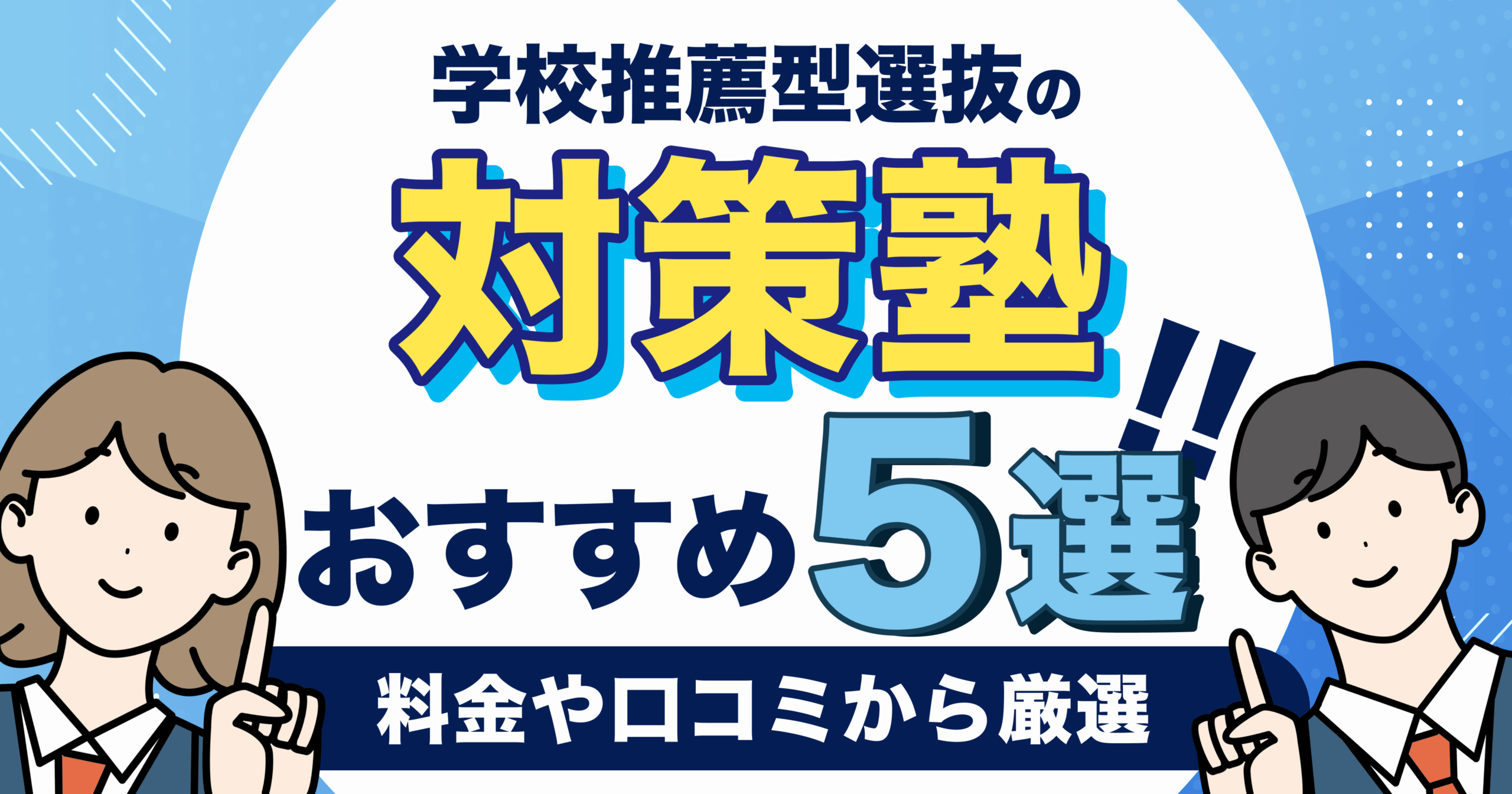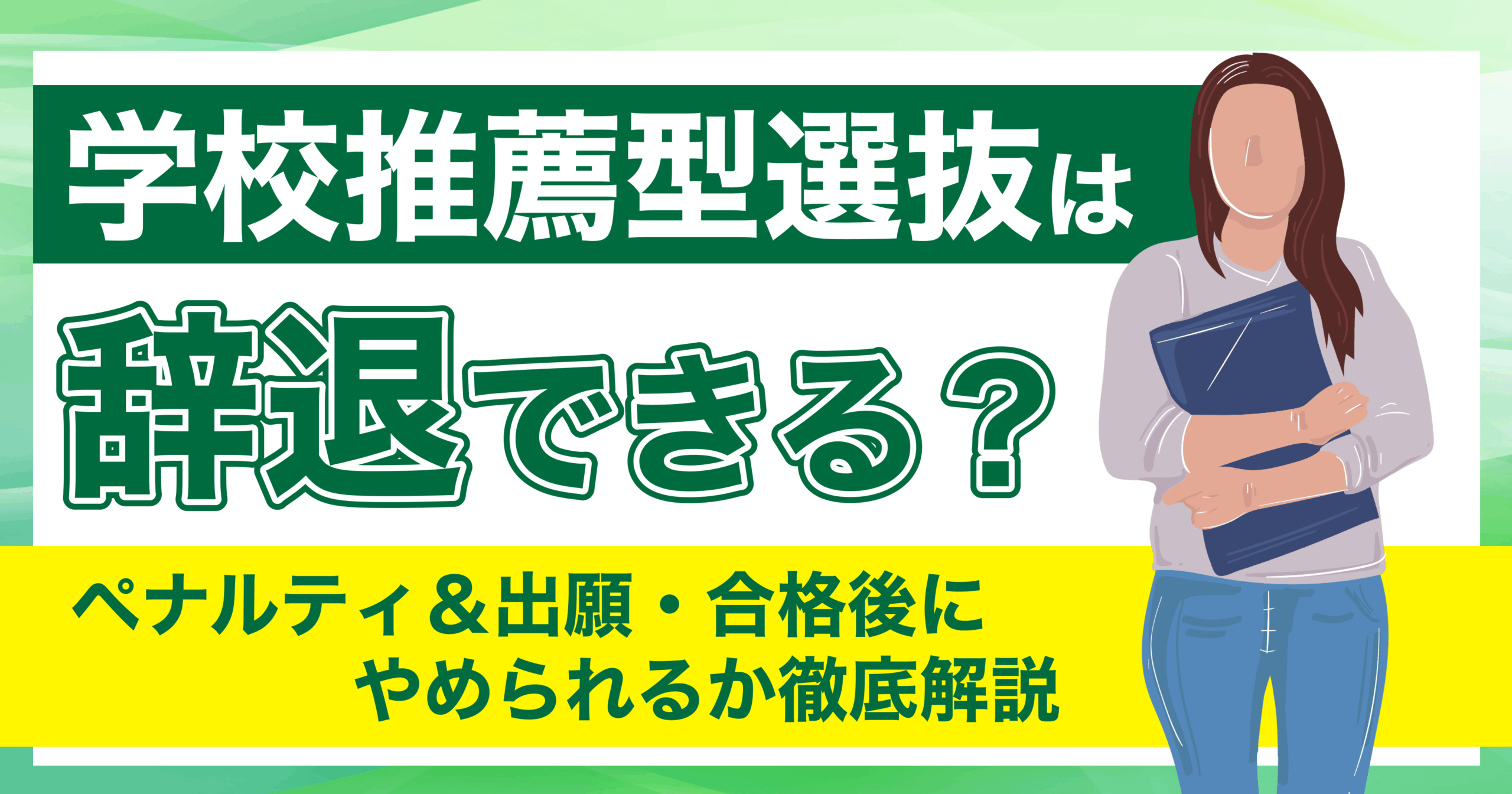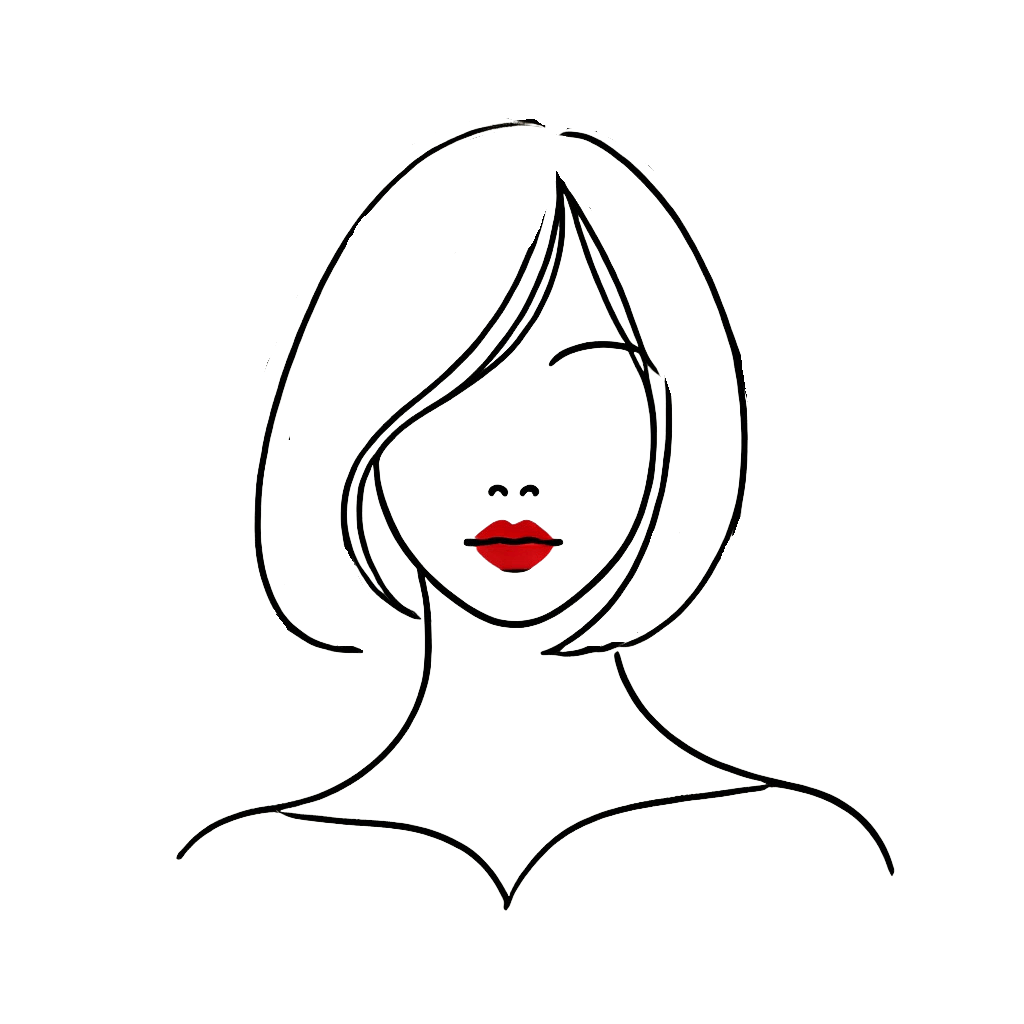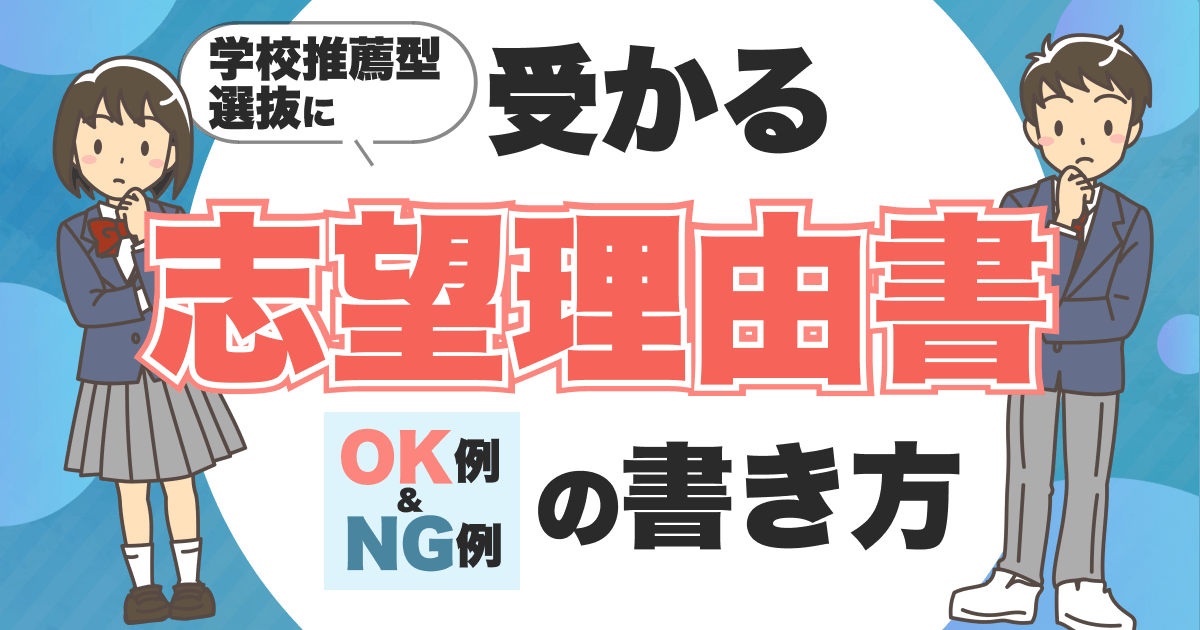「学校推薦型選抜って、どんな入試なんだろう?」
「受けるのに条件が厳しかったりするのかな…」
大学入試の選択肢としてよく聞く「学校推薦型選抜」。しかし、詳しい入試の内容やそもそも自分が受けられる試験なのか、あいまいな人もいますよね。
学校推薦型選抜は仕組みを正しく理解して対策すれば、合格の可能性を大きく広げられる試験です。
本記事では試験内容や出願条件・合格率なども交え、学校推薦型選抜の特徴を解説します。この記事を読めば、学校推薦型選抜がどんな試験なのか、明確になりますよ。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)は、出身高校の校長からの推薦に基づき、高校3年間の学習成績、課外活動、学びへの意欲などを総合的に評価する入試方式です。入学者数は、総合型選抜と合わせると全体の5割を超えています。
種類は公募制と指定校制に大別され、指定校制は合格率が高い傾向にあるものの、基本的に専願(合格したら必ず入学)が条件となります。
出願時には、高校1年生から3年生1学期までの評定平均値の基準を満たすことが不可欠であり、部活動や資格取得などの課外活動も重要な評価対象です。
試験内容は、高校での取り組みを評価する書類審査(調査書、推薦書、志望理由書など)、小論文試験、面接試験が中心です。国公立大学などでは、学力試験として大学入学共通テストなどが課される場合もあります。
合格を勝ち取るためには、日々の真面目な学習態度(高い評定平均)と、主体的な行動実績、コミュニケーション能力が重要視されます。仕組みを正しく理解し、早期に対策を始めることが合格の可能性を広げます。
なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。
かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。
効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。
\ 4つの質問に答えるだけ /
本記事の要点を音声でチェック!
学校推薦型選抜とは?
学校推薦型選抜とは、出身高校の校長からの推薦に基づき、大学からの評価を受ける入試方式です。2021年度の大学入試改革により、従来の「推薦入試」から現在の名称に変更されました。
学校推薦型選抜では、下記の点などが総合的に評価されます。
- 高校3年間の学習成績
- 課外活動での取り組み
- 学びへの意欲
文部科学省の調査によれば、国公私立大学入学者のうち、学校推薦型選抜と総合型選抜を合わせた年内入試での入学者は全体の5割を超えています。
参考:令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要:文部科学省
ここでは、学校推薦型選抜と混同されやすい、下記2つの入試方式との違いを解説します。
なお、学校推薦型選抜のメリットとデメリットを詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。
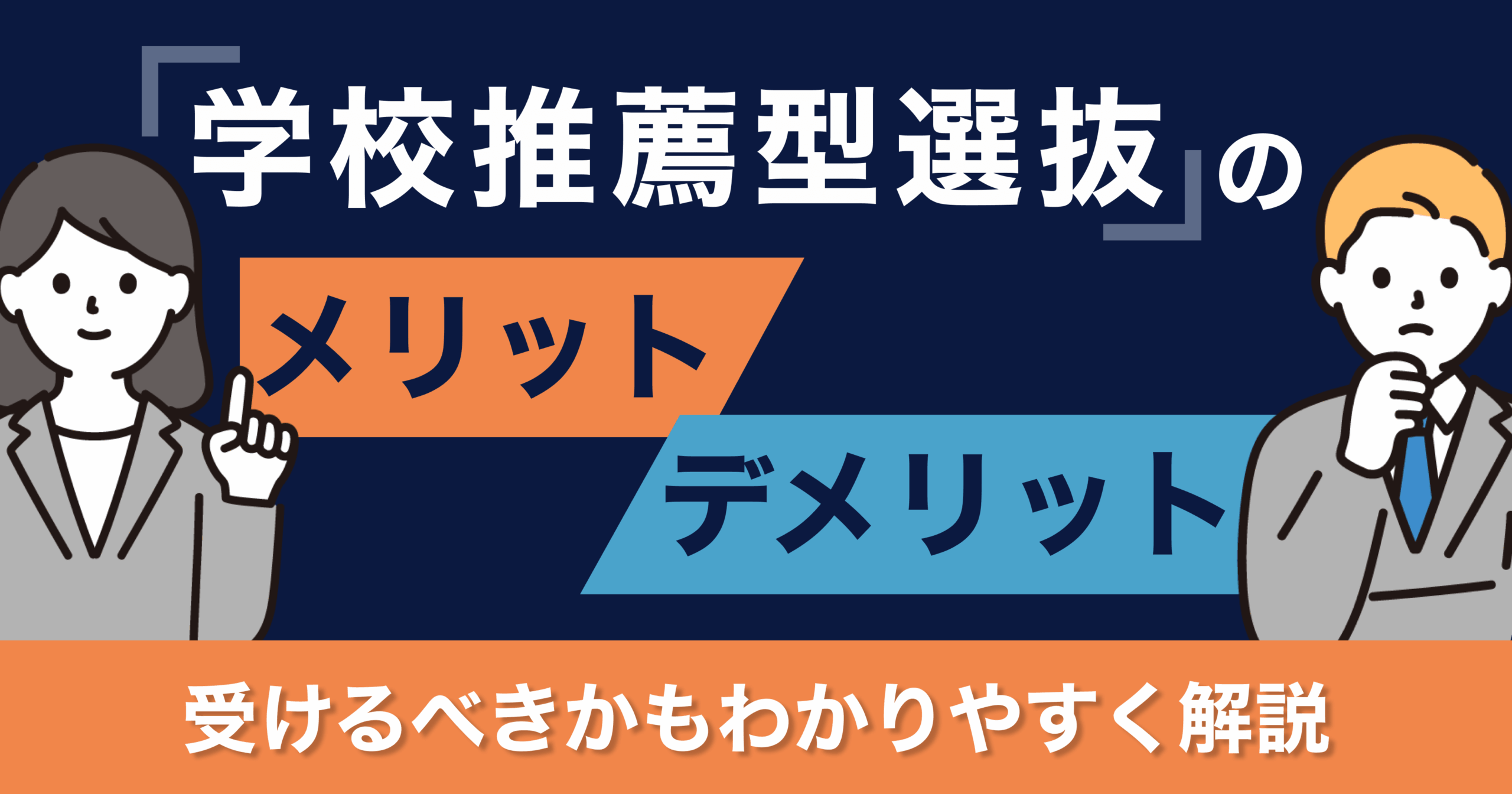
総合型選抜との違い
学校推薦型選抜と総合型選抜の最も大きな違いは「学校長の推薦」が必須かどうかです。その他、選考スケジュールや方法にも違いがあり下表にまとめました。
| 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | |
|---|---|---|
| 推薦の有無 | 学校長の推薦が必須 | 自己推薦で出願可能 |
| 主な選考時期 | 11~12月 | 9~10月 |
| 選考方法 | 書類・面接・小論文が中心 | 大学により多様(プレゼン、グループ討議など) |
上表のように、学校推薦型選抜は「学校長の推薦」が必須である点と、総合型選抜よりも選考スケジュールが遅い点が大きな特徴です。
学校推薦型選抜と総合型選抜の違いをより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。
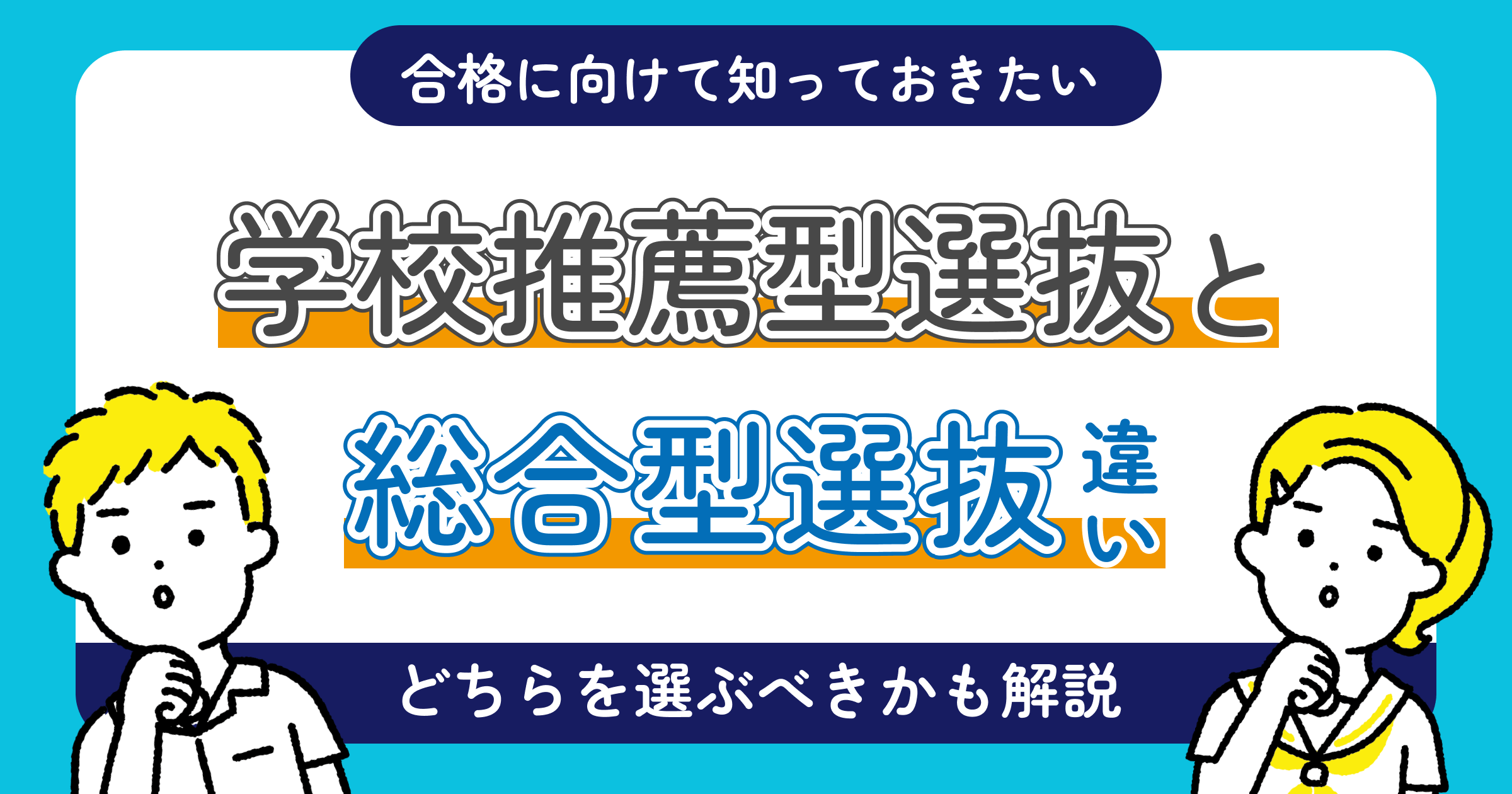
一般選抜との違い
一般選抜と学校推薦型選抜の違いは、評価の重点が「学力試験」か「高校での取り組み」かという点にあります。学校推薦型選抜は、高校3年間の努力の積み重ねが評価される入試です。2つの入試形式の違いを下表にまとめました。
| 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | |
|---|---|---|
| 評価の重点 | 高校3年間の取り組み(評定、課外活動など) | 主に学力試験の結果 |
| 推薦の有無 | 学校長の推薦が必須 | 不要 |
| 主な出願条件 | 評定平均などの基準あり | 基本的になし |
| 主な選考時期 | 11~12月 | 1~3月 |
| 選考方法 | 書類・面接・小論文が中心 | 主に学力試験 |
学校推薦型選抜は学力試験は評価の一部にすぎず、高校生活全体の頑張りが評価される入試制度と言えるでしょう。
学校推薦型選抜の種類
学校推薦型選抜は下記の2つに大別されています。
種類ごとで出願条件や選考過程が異なります。それぞれ詳しく解説します。
公募制推薦
公募制推薦とは、大学が定めた出願条件を満たし、高校長の推薦があればどの高校からでも出願できる入試方式です。
公募制推薦には、主に次の特徴があります。
- 大学が示す評定平均などの成績基準が設けられることが多い
- 全国の高校生がライバルになるため、競争率が高くなる傾向がある
- 「公募制一般推薦」と、スポーツや文化活動での実績を評価する「公募制特別推薦」の2種類に分けられる場合がある
- 他の大学との併願を認めている大学も増えている
公募制推薦は、門戸は広いものの、個人の実力が試される競争率の高い選抜方式と言えるでしょう。
指定校制推薦
指定校制推薦とは、大学が指定した特定の高校の生徒のみが出願できる入試方式です。
指定校制推薦の主な特徴は、下記のとおりです。
- 大学から各高校へ与えられる推薦枠(1〜数名)が限られており、まず校内選考を通過する必要がある
- 校内選考を通過すれば、合格率は高い傾向にある
- 基本的に、合格したら必ず入学する「専願」が条件となる
- 主に私立大学で実施されている
指定校制推薦は、高校内での推薦枠を勝ち取ることが最初の関門で、通過すれば合格がほぼ約束される選抜方式です。
学校推薦型選抜の出願条件
学校推薦型選抜に出願するには、大学が定める条件をクリアする必要があります。誰でも出願できるわけではありません。
ここからは学校推薦型選抜の主な出願条件を、3つにまとめて解説します。
なお、上記を含め学校推薦型選抜の出願条件をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
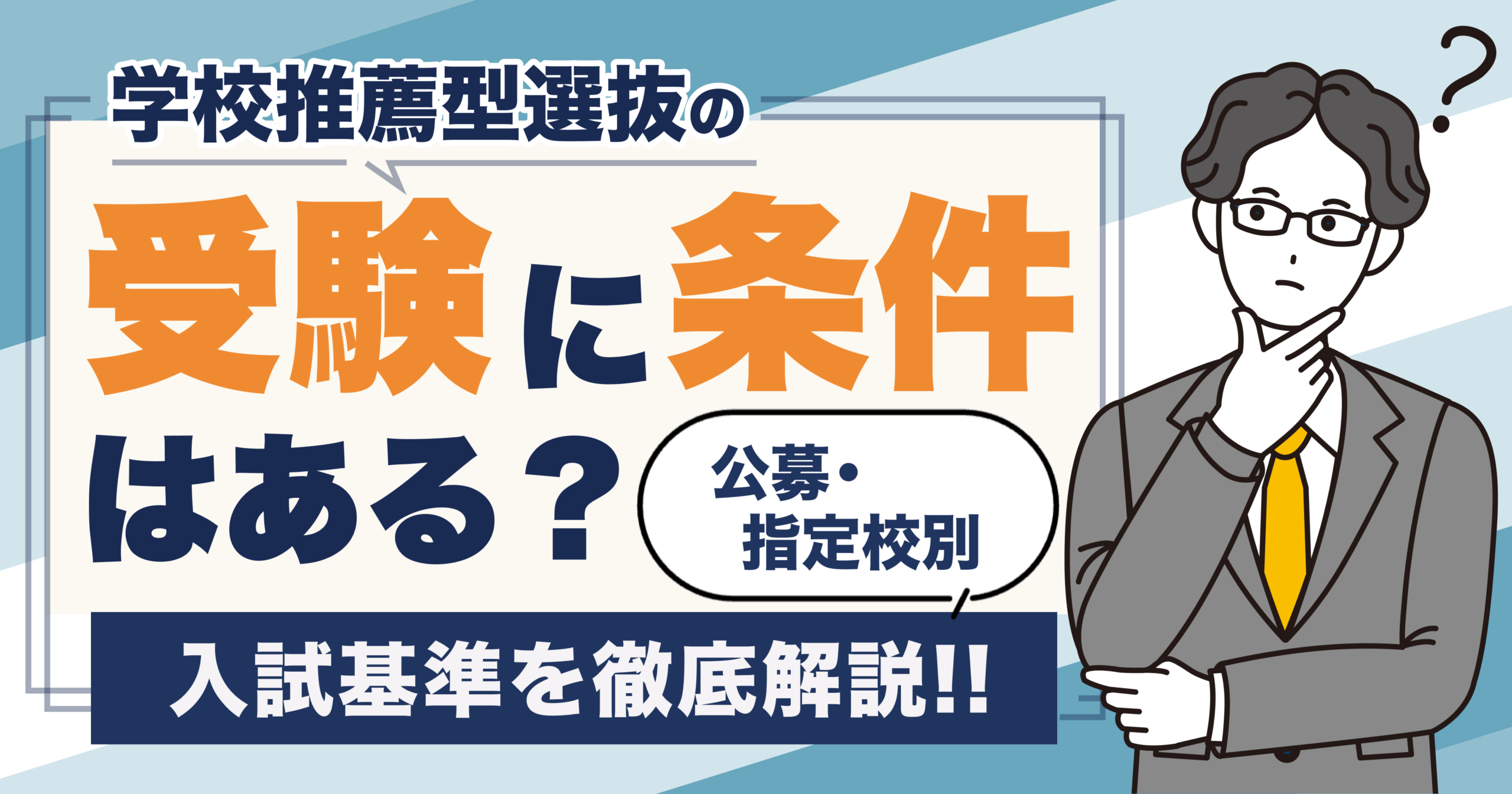
評定平均値の基準を満たす
評定平均値とは、高校1年生から3年生の1学期(または前期)までの成績を5段階評価で数値化したものです。学校推薦型選抜において欠かせない出願条件となります。
大学や学部ごとに「全体の評定平均値が4.0以上」といった基準が設けられているのが一般的です。また、大学によっては「英語の評定が4.3以上」のように、学部に関連する特定の教科の評定が問われる場合もあります。
評定平均は、短期間の勉強で上げられるものではありません。高校入学時から日々の授業に真剣に取り組み、定期テストで着実に点数を重ねていく継続的な努力が不可欠です。受験生の学習に対する真摯な姿勢を示す指標です。
学校推薦型選抜における評定平均や欠席日数の影響度合いをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
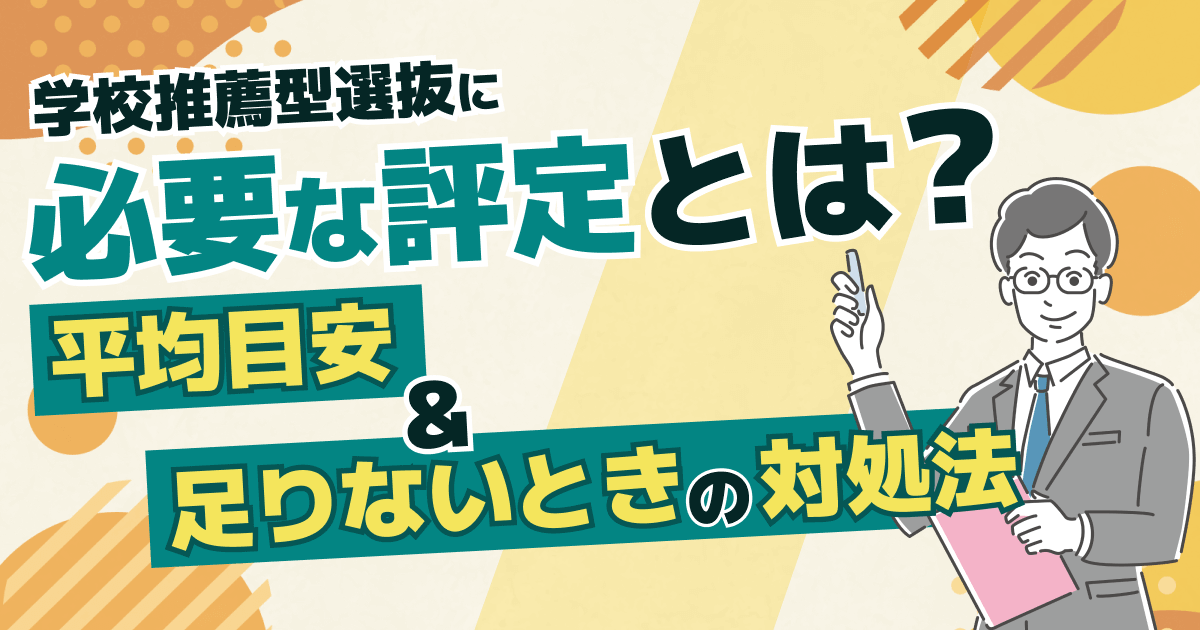
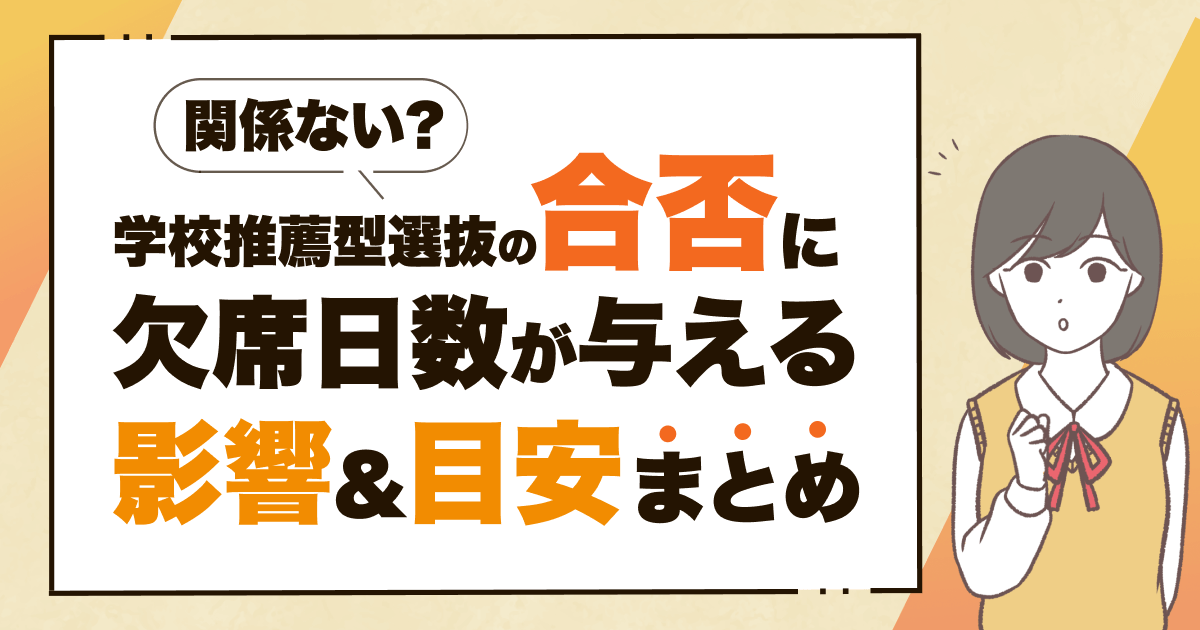
課外活動・資格取得の評価を得る
学業成績だけでなく、高校時代に打ち込んだ課外活動や取得した資格も、自分をアピールする重要な要素となります。
評価の対象となる活動例は、下記のとおりです。
課外活動や資格取得は、主体性やリーダーシップを大学に伝えるための機会です。出願時期から逆算して、早めに実績作りや資格取得の準備を始めましょう。
専願か併願かを調べる
出願前に必ず確認すべきなのが、その大学が「専願」なのか「併願」なのかという点です。
| 専願 | 合格した場合、必ずその大学に入学することが条件 |
| 併願 | 他の大学も受験することが可能 |
指定校制推薦は基本的に専願ですが、公募制推薦では併願可能な大学も増えています。専願の大学に合格して入学を辞退すると、出身高校の後輩がその大学の推薦を受けられなくなるなどのペナルティが発生する場合があるため、慎重な判断が必要です。
学校推薦選抜の試験内容
ここからは学校推薦型選抜の主な試験内容を4つにまとめて解説します。なお、下記のうちどんな試験が実施されるかは、大学や学部によってさまざまです。
書類審査(調査書・推薦書)
書類審査は、出願時に提出する書類によって、受験生の高校での取り組みや人柄を評価するものです。
審査の対象となる主な書類は、下表のとおりです。
| 調査書 | 評定平均値や授業の出欠状況、特別活動の記録などが記載された高校が作成 |
| 推薦書 | 高校の先生が、受験生の学業成績や人柄について記述 |
| 志望理由書 | なぜその大学・学部で学びたいのか、自分の言葉で熱意を記す |
| 自己推薦書 エントリーシート | 大学によっては、志望理由書とは別に、自己PRを記載する書類が求められる場合がある |
上記の書類は、面接の際の質問材料にもなるため、一貫性のある内容を丁寧に作成することが重要です。
調査書や推薦書についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
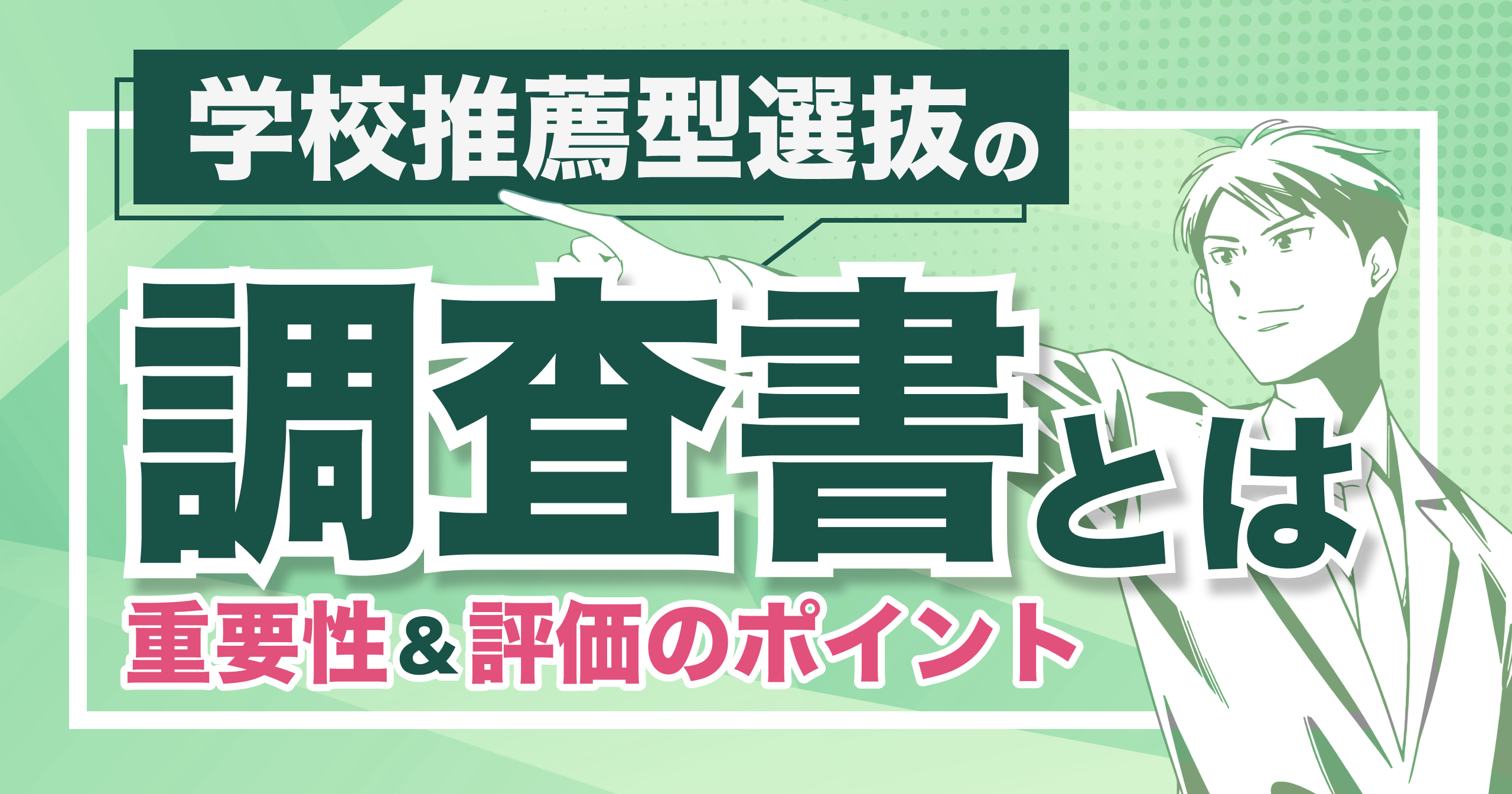

小論文試験
小論文試験は、与えられたテーマに対して、自分の意見を論理的に記述する能力を評価する試験です。
小論文試験には、主に次の特徴があります。
- 問われる内容:志望理由に関するものから、時事問題、学部に関連する専門的なテーマまで多岐にわたります。
- 評価基準:文章の論理性、表現力、テーマに関する知識、そして独自の発想などが評価されます。
知識量だけでなく、物事を多角的に捉え、自分の考えを的確に表現する力が求められます。
面接試験
面接試験は、大学の教員と直接対話し、人間性や学習意欲を伝える重要な機会です。提出書類の内容を深掘りされることも多く、論理的思考力やコミュニケーション能力が総合的に評価されます。
面接試験の主な特徴は、下記のとおりです。
- 面接の形式
- 受験生1人で行う「個人面接」のほか、複数の受験生が同時に受ける「集団面接」や、特定のテーマについて討議する「グループディスカッション」などがあります。
- よく聞かれる質問
- 「志望理由」「高校生活で頑張ったこと」「入学後の目標」「最近気になったニュース」などが定番の質問です。
- 評価されるポイント
- 学習への意欲、人柄、コミュニケーション能力に加え、論理的思考力、表現力、そして大学の教育方針(アドミッションポリシー)との適合性などが総合的に評価されます。
面接官との対話を通じて、大学が求める人物像と自分が合致していることを示す最終的なアピールの場です。自分の言葉で受け答えができるよう、準備をして臨むことで評価を得られます。
学力試験
学校推薦型選抜では、学力試験を課さない大学も多いです。しかし特に国公立大学では、学力試験が求められる場合があります。
学力試験には、主に次のような形式があります。
- 大学入学共通テストの成績を利用する
- 大学独自の教科・科目試験を実施する
- 思考力や判断力を測るための適性検査を行う
- 英語資格・検定試験(英検®など)のスコアを評価に加える
- 特定のテーマについて発表するプレゼンテーションや口頭試問、実技試験を行う
志望する大学でどの形式の学力試験が課されるのか、募集要項で必ず確認しておきましょう。
学校推薦型選抜で共通テストを実施する大学を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
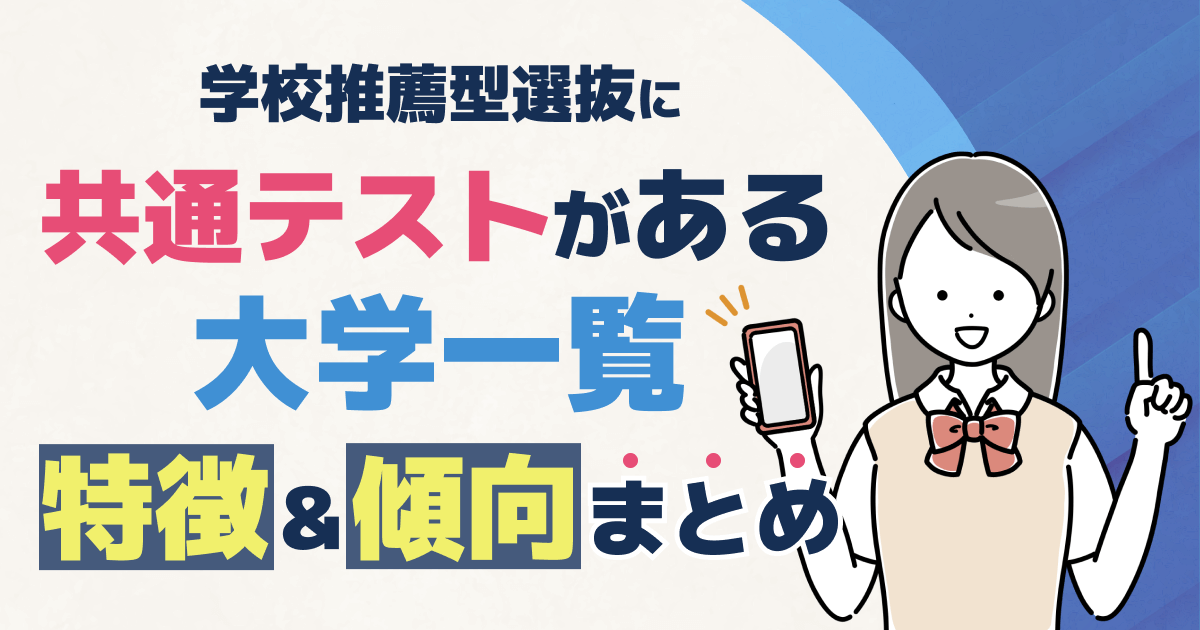
学校推薦型選抜の合格率
学校推薦型選抜の合格率は、公募制と指定校制で異なります。
公募制推薦は、大学や学部によって倍率が左右され、一概に「合格率が高い・低い」とは言えません。指定校制推薦は、校内選考を通過すれば合格率は高い傾向にあります。大学と高校の信頼関係に基づいているためです。
学校推薦型選抜の倍率や合格率をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
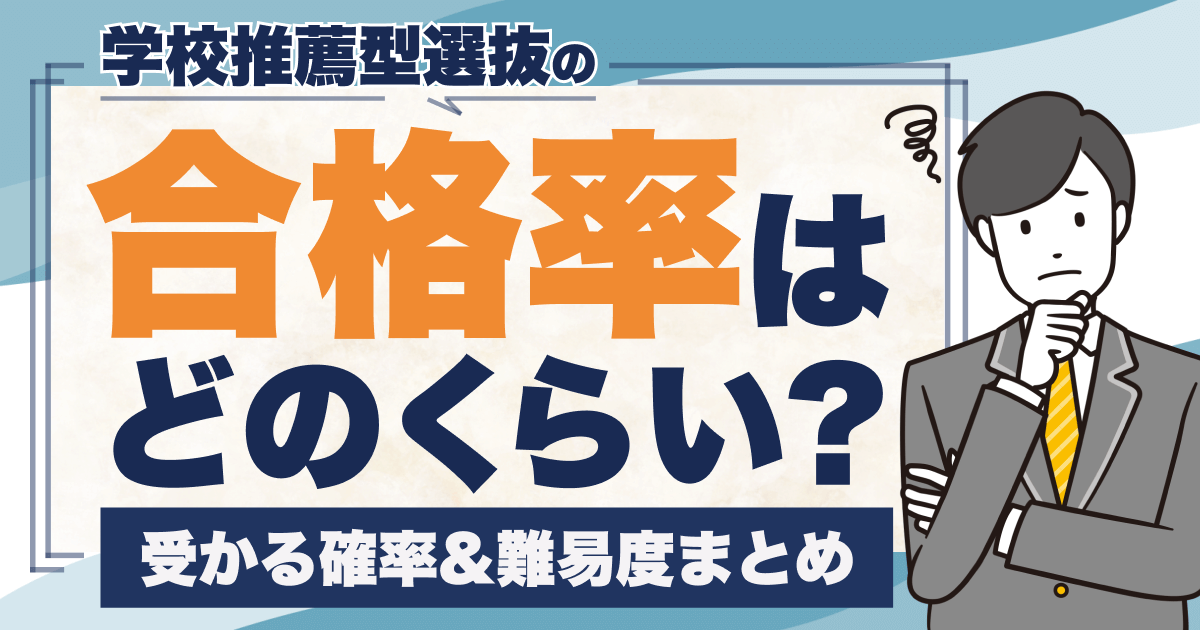
上記を踏まえ、ここからは学校推薦型選抜に受かりやすい人・落ちやすい人の特徴をそれぞれ解説します。
落ちやすい人の特徴
学校推薦型選抜で不合格になってしまう人には、準備不足や自己分析の甘さなどの共通点が見られます。自分に当てはまっていないか、確認してみましょう。
まずは、出願条件をギリギリで満たしている場合です。評定平均が出願基準ギリギリだと、他の受験生との比較で不利になる可能性があります。大学側は、余裕を持って基準をクリアしている学生を「入学後も安定して学習に取り組める」と評価する傾向があります。
志望理由が曖昧で、熱意が感じられない場合も不合格につながりやすいです。「貴学の教育理念に共感した」という抽象的な理由だけでは熱意は伝わりません。なぜその大学でなければならないのか、自分の経験と結びつけて具体的に語れないと他の受験生に埋もれてしまいます。
学業成績だけでなく、高校での活動実績が乏しいと、人柄やポテンシャルを評価されにくくなります。部活動やボランティアなど、何かに打ち込んだ経験は主体性の証明になります。
学校推薦型選抜に落ちる確率を詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。
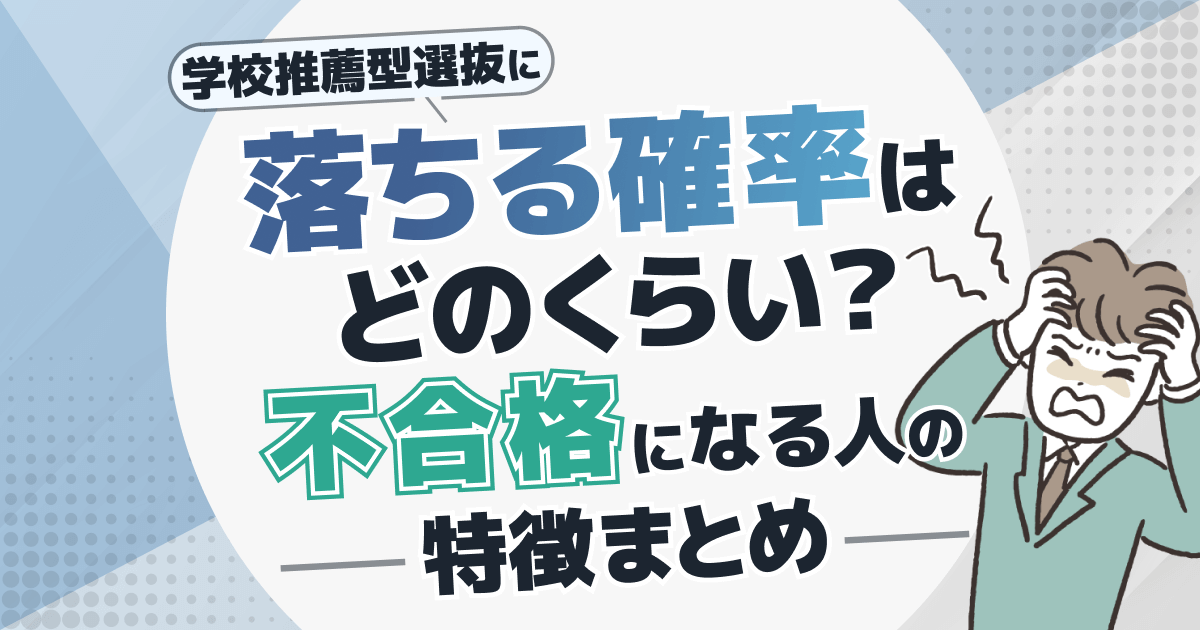
また落ちた場合の対策、不合格後に志望校を目指す方法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

受かりやすい人の特徴
学校推薦型選抜で合格を勝ち取る受験生には、日々の努力と入念な準備が見られます。
高い評定平均を維持していることは、高校3年間の真面目な学習態度の証明です。大学側は、学業への意欲が高い学生として高く評価します。
主体的に行動した経験や実績がある点も評価されます。部活動の部長や生徒会役員、ボランティア活動など自ら考えて行動した経験は、リーダーシップや主体性の証明となり、高評価の対象です。
コミュニケーション能力が高いことも、受かりやすい人に見られる特徴です。面接でのハキハキとした受け答えや、質問の意図を正確に理解して的確に回答できる能力は、大学での学習や活動においても不可欠なスキルと見なされます。
学校推薦型選抜に受かりやすい人の特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
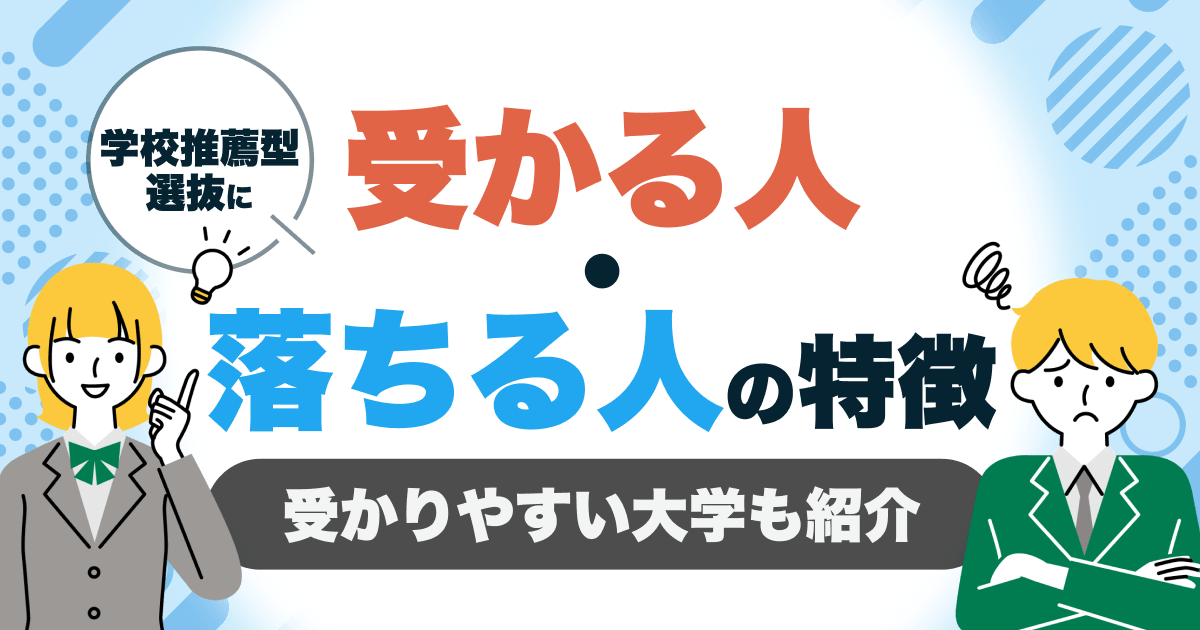
学校推薦型選抜の受験スケジュール
学校推薦型選抜は下記のスケジュールで進められています。
なお、学校推薦型選抜は一般選抜よりも早く、年内に合否が決まるのが大きな特徴です。上記の各スケジュールを詳しく解説します。
1.校内選考
学校推薦型選抜の中で指定校制推薦を希望する場合、大学への出願に先立って、高校内での選考を通過する必要があります。大学から高校に与えられる推薦枠は「1学部につき1名」などに限られているため、校内選考を突破できるかどうかが、合格に影響します。
校内選考は、3年生の夏休みから秋にかけて行われるのが一般的です。希望者は、校内の進路指導部などに意思を伝え、エントリーします。その後、先生方による「推薦委員会」などの会議で、下記の点が総合的に評価され、推薦候補者が正式に決定されます。
- 評定平均値
- 最も重要な評価基準です。希望者が多い場合は、評定平均がわずか0.1違うだけで当落が分かれることもあります。
- 課外活動の実績
- 部活動や生徒会活動、ボランティア活動など、学業以外での主体的な取り組みが評価されます。
- 生活態度
- 授業への出席状況や提出物など、日頃の真面目な学校生活も重要な判断材料となります。
校内選考を通過して初めて、大学への出願資格を得ることができます。
2.出願・試験の受験
校内選考を通過すると、いよいよ大学への出願です。
- 出願時期
- 文部科学省の方針により、11月1日以降に受付が開始されます。
- 出願書類
- 調査書や推薦書、志望理由書など、大学の指示に従って不備のないよう準備します。
- 試験日程
- 11月から12月にかけて、小論文や面接などの試験が実施されます。
国公立大学などで大学入学共通テストが課される場合は、1月に共通テストを受験し、結果も合否判定に利用されます。
3.合格発表と入学手続き
試験を経て、最終的な合否が発表されます。
- 合格発表時期
- 12月1日以降に発表されるのが一般的です。ただし、共通テストを課す大学では、2月頃になる場合もあります。
- 入学手続き
- 合格した場合は、定められた期限までに入学金や授業料の納付、必要書類の提出といった手続きを行います。
万が一不合格だった場合に備え、すぐに一般選抜の準備に切り替えられるよう、心づもりをしておくことも大切です。
学校推薦型選抜に受かるのに必要な要素を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
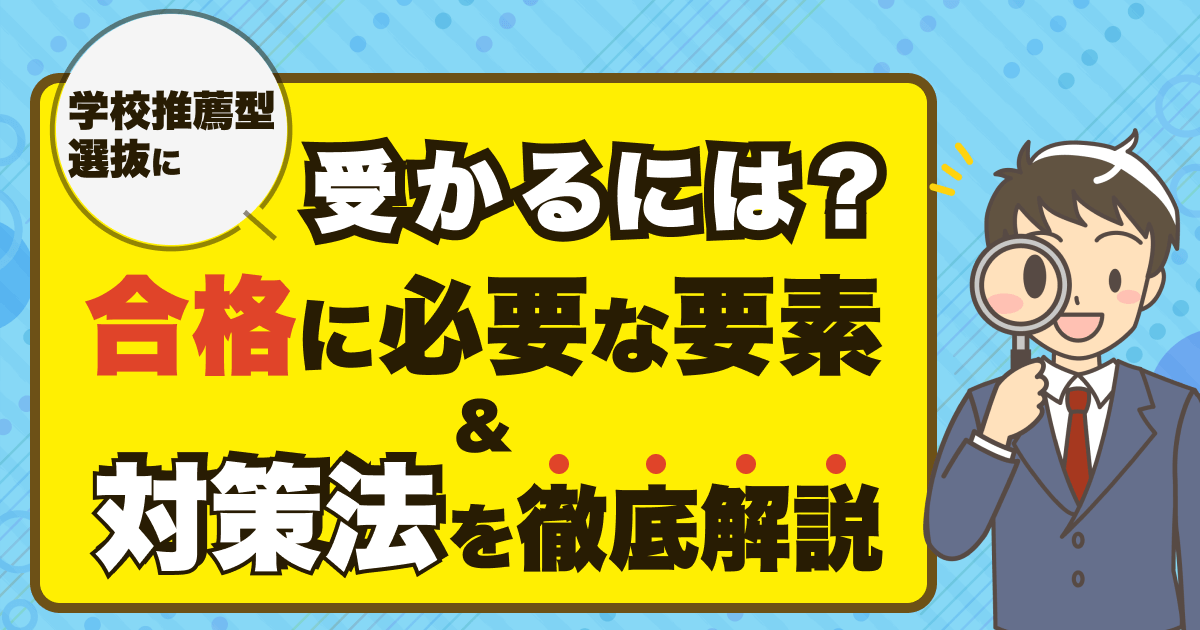
【試験別】学校推薦型選抜の対策法
学校推薦型選抜の合格を勝ち取るためには、試験内容に合わせた適切な対策が不可欠です。ここからは次の試験別に、学校推薦型選抜の具体的な対策法を解説します。
上記を含め、学校推薦型選抜の対策法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
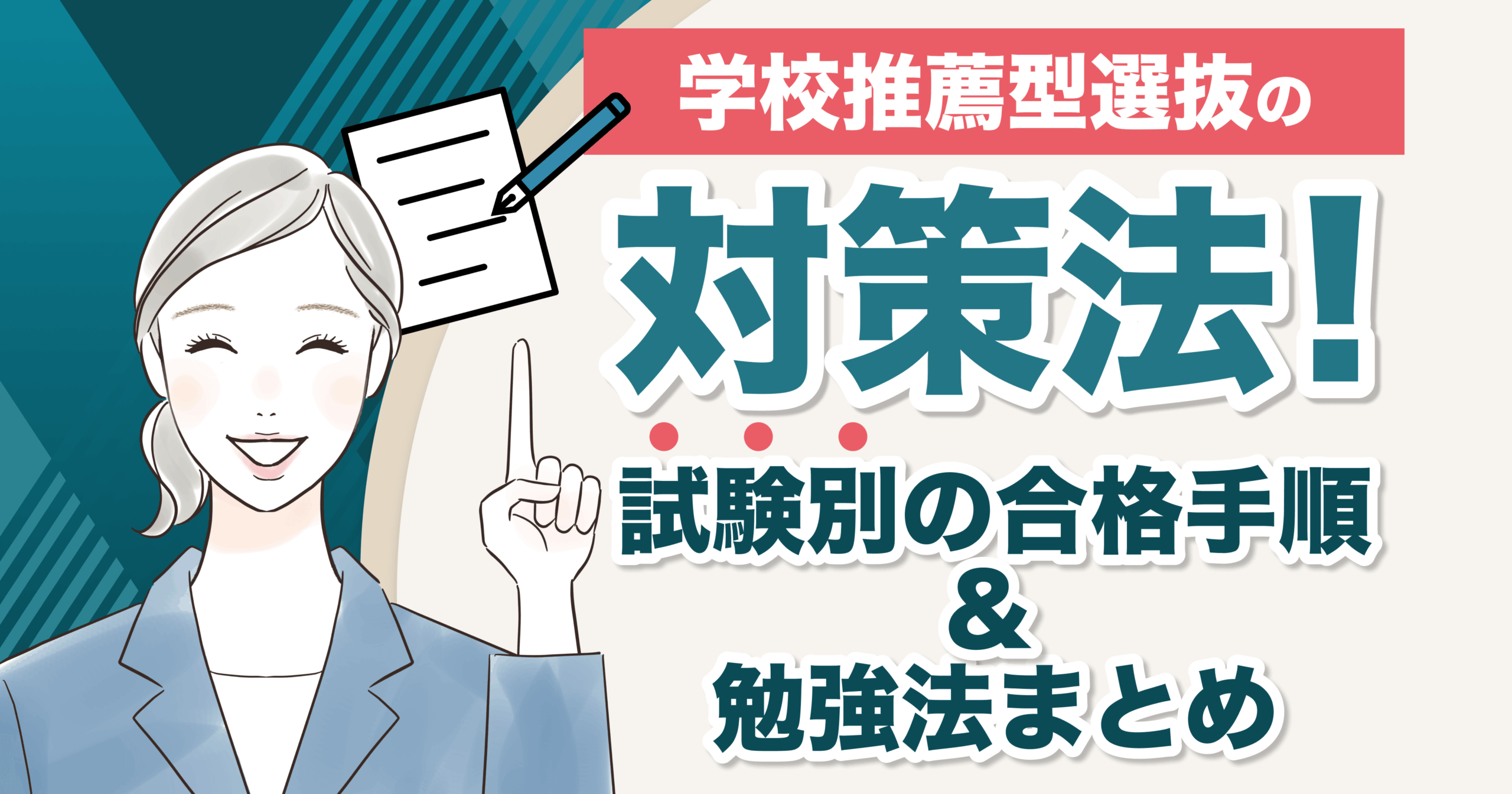
書類審査を突破する3つのポイント
書類審査は、高校生活の頑張りを大学に伝える最初の試験です。
まず、評定平均値を上げることが基本です。日々の学習への取り組みを示す最も客観的な指標で、高校1年生の時から定期テスト対策を怠らず、授業に真剣に取り組む姿勢が評価に直結します。
部活動や生徒会、ボランティアなどの課外活動へ積極的に参加することも重要です。学業以外の活動は、受験生の主体性や人間性をアピールする絶好の機会となります。
高校での経験を基に、熱意の伝わる志望理由書を作成することが求められます。「なぜこの大学でなければならないのか」を、自分の言葉で具体的に記述し、熱意を伝えましょう。
志望理由書や申込書の書き方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
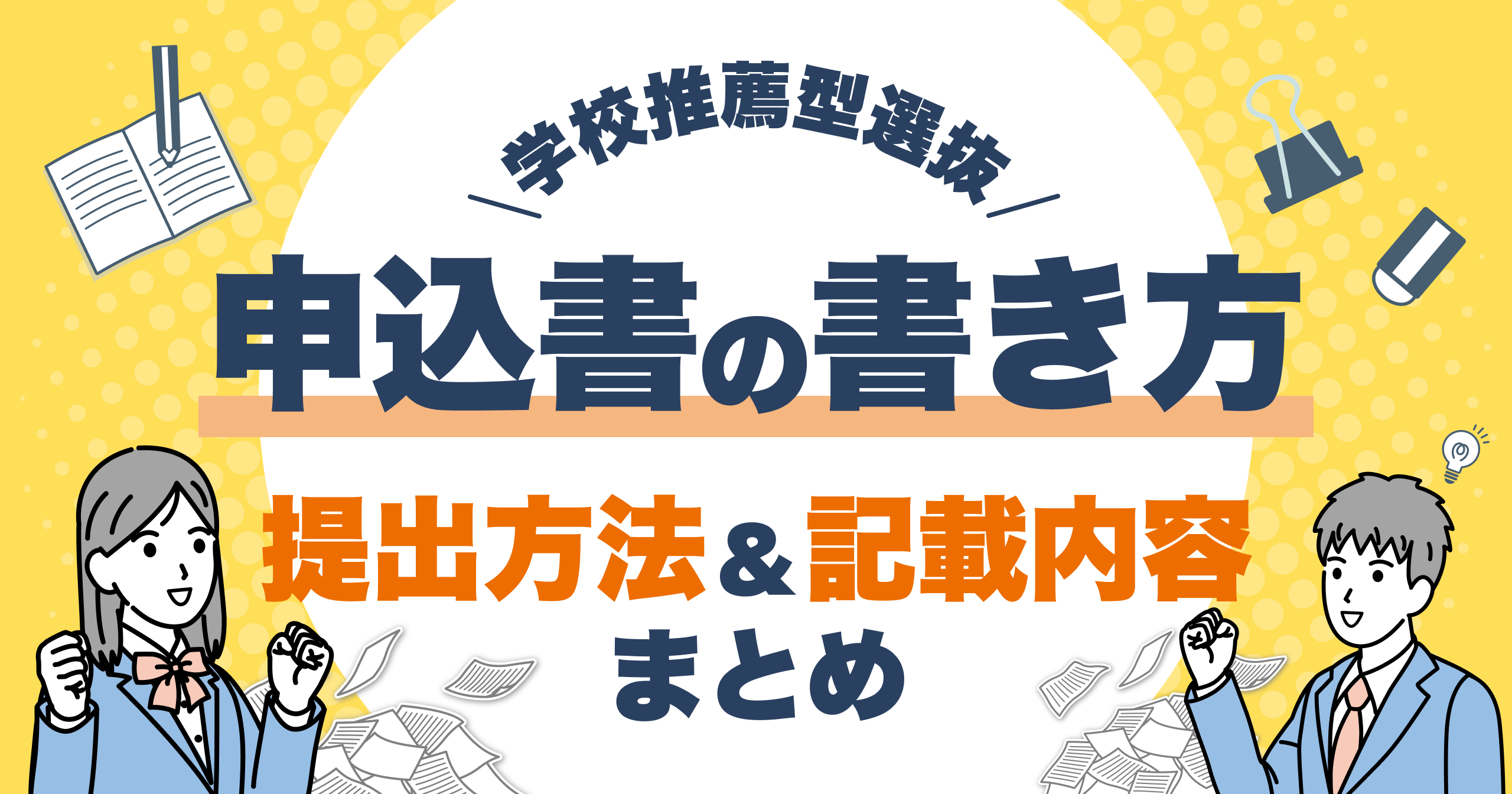
説得力のある小論文を書くコツ
小論文は、思考力や表現力を評価するための試験です。「序論・本論・結論」という基本構成をマスターし、論理的な文章展開を心がけることが大切です。日頃からニュースに関心を持ち、志望学部に関連するテーマの知識を深めておく必要があります。
知識をインプットしたら、志望校の過去問を活用して実践練習を積みましょう。書いた小論文は、必ず学校の先生や塾の講師に添削してもらい、客観的な視点で改善を重ねることが合格への近道です。
本番を想定し、制限時間内に書き上げる練習も忘れてはいけません。
小論文試験の対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。
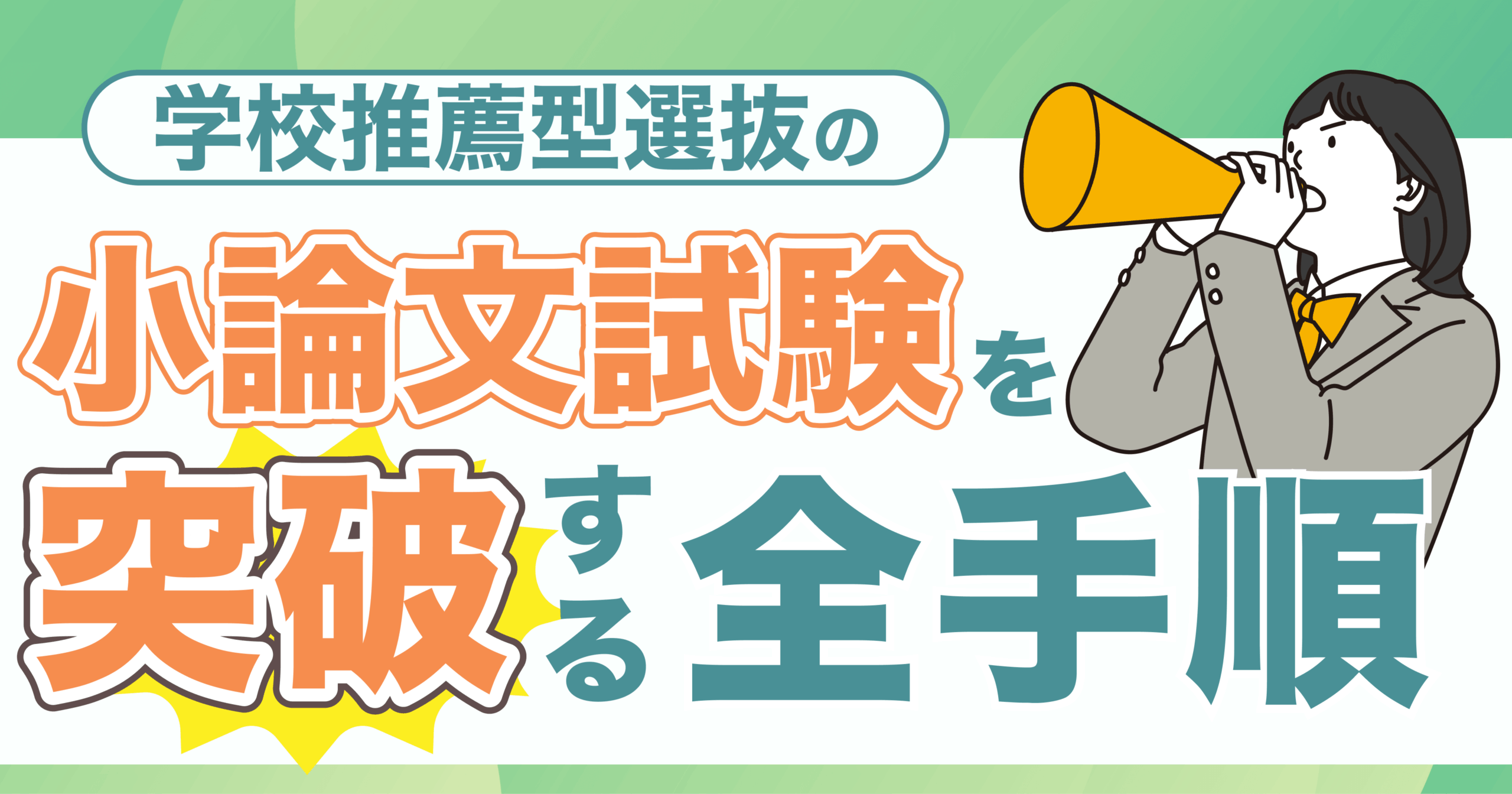
面接で好印象を得る準備
面接は、人柄や学習意欲を直接アピールできる貴重な機会です。入念な準備が、自信と好印象につながります。
まずは、自己分析を深めることから始めましょう。「なぜこの大学なのか」「高校生活で何を頑張ったか」など、自分自身の経験や考えを整理し、明確に説明できるように準備します。想定される質問への回答を準備しておくと、心に余裕が生まれます。
準備が整ったら、先生や友人にお願いして模擬面接を繰り返し行い、人前で話すことに慣れておきましょう。入退室のマナーや身だしなみ、正しい言葉遣いも重要な評価ポイントです。
面接試験の対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
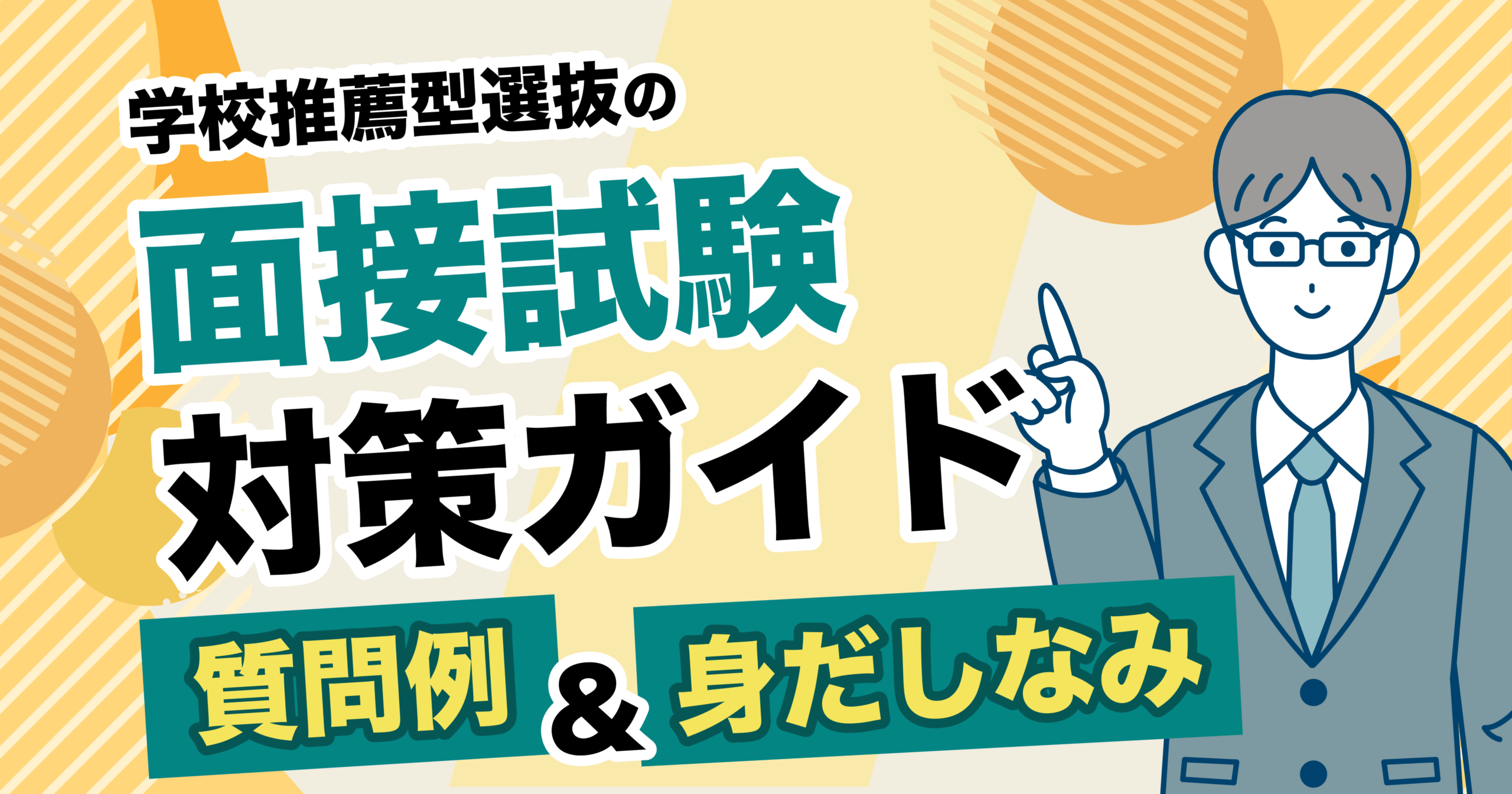
学力試験で高得点を得る方法
特に国公立大学や一部の私立大学では、基礎学力を測るための学力試験が課されます。早期からの対策が合格の鍵を握ります。
教科書レベルの基礎学力を徹底的に固めることが重要です。基礎学力が応用問題への対応力につながります。大学独自の試験が課される場合は、過去問を研究して出題傾向を掴み、的を絞った対策を行いましょう。
国公立大学を志望する場合は、一般選抜の受験生と同様に、大学入学共通テストで高得点を目指す必要があります。また、英検などの英語資格・検定試験のスコアが評価対象となる大学も多いため、計画的に取得を目指すのもおすすめです。
まとめ
本記事では、複雑で分かりにくい学校推薦型選抜の全体像を、基礎知識から具体的な対策まで解説しました。公募制と指定校制の違い、合否を分ける評定平均の重要性、そして書類審査・小論文・面接といった各選考の突破法まで、合格に必要な情報を網羅しています。
学校推薦型選抜は、高校3年間の努力が正当に評価される入試方式です。この記事で得た知識を元に、一日でも早く対策を始めることが、ライバルと差をつける何よりの武器になります。
みなさんの高校生活の頑張りが志望校合格に繋がることを、心から応援しています。
こちらの記事もおすすめ