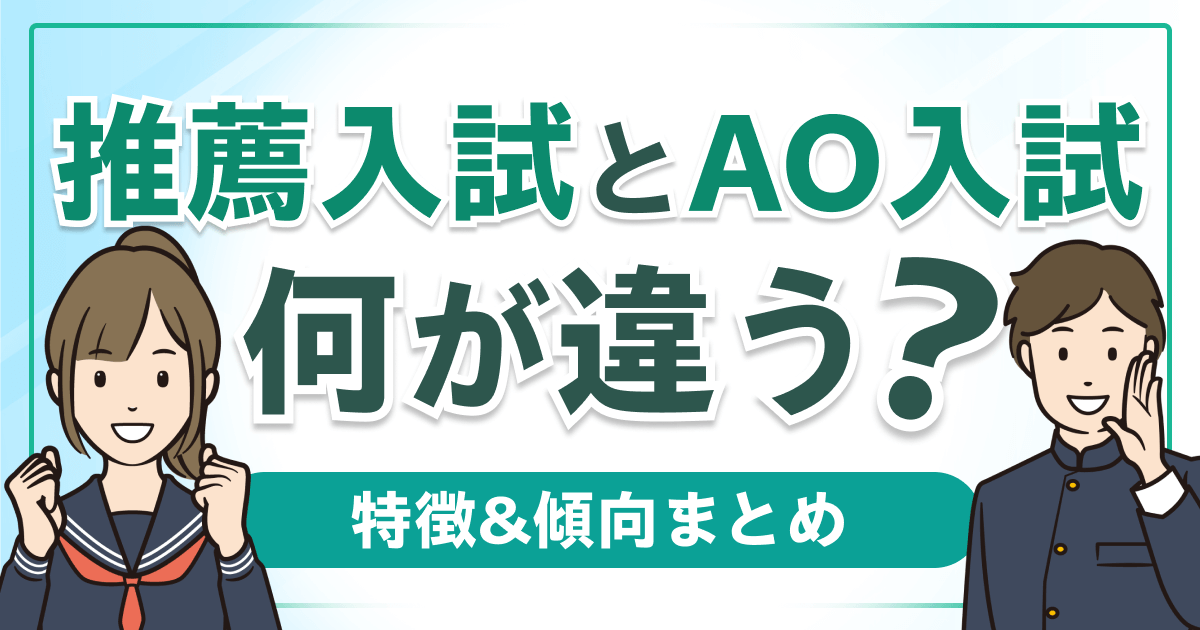「AO入試と推薦入試って何が違うの?」
「こっちの方が受かりやすい、みたいなのはあるのかな…」
「〜推薦」や「〜入試」など最近、似たような名称の入試方式が増えているため、違いがあいまいになりがちです。
特に、推薦入試とAO入試は同じものなのか、違う試験なのかわからない人は多いですよね。
そこで本記事では特徴を交え、AO入試と推薦入試の違いを解説します。AO入試と推薦入試のどちらを受けるべきかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- AO入試は総合型選抜に名称が変更された
- 熱意の高い志望理由がある人に向いている
- 一般入試よりも難易度が低い
なお、推薦入試での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。
かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。
効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。
\ 4つの質問に答えるだけ /
本記事の要点を音声でチェック!
AO入試は推薦入試の1つ
「AO入試」は、指定校推薦や公募推薦などと同じく「推薦入試」の一つです。受験生の人物像や意欲、将来の目標など、学力以外の能力を総合的に評価して合否を判定します。
「AO入試」という名称に「推薦」の文字が含まれていないため誤解されがちですが、一般入試のような学力中心の試験ではなく推薦入試の一種です。
また、後ほど詳しく解説しますが「AO入試」は数年前まで使われていた入試方式の名称まで名称です。現在では「総合型選抜」に名前を変えています。
名称が変わってからの期間が浅いため、入試方法について調べたり誰かに相談するときに「AO入試」と「総合型選抜」のどちらも使われることがあります。これにより混乱してしまう受験生は少なくありません。
推薦入試の特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
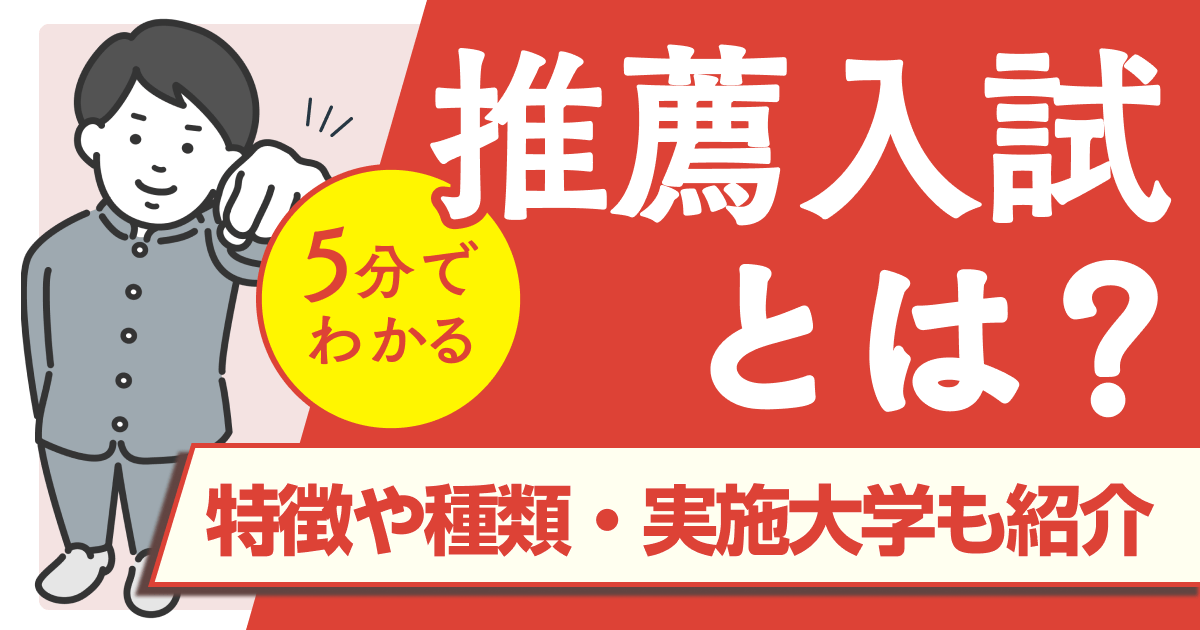
2020年度より総合型選抜に名称変更
AO入試は2020年度を境に「総合型選抜」という名称に変更されました。
旧AO入試である総合型選抜は、詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせて受験者を評価する入試方式です。入学志願者の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識等を総合的に評価・判定します。
合否判定に当たっては「入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価・判定する」と文部科学省からも公表されています。
具体的な名称変更の経緯を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
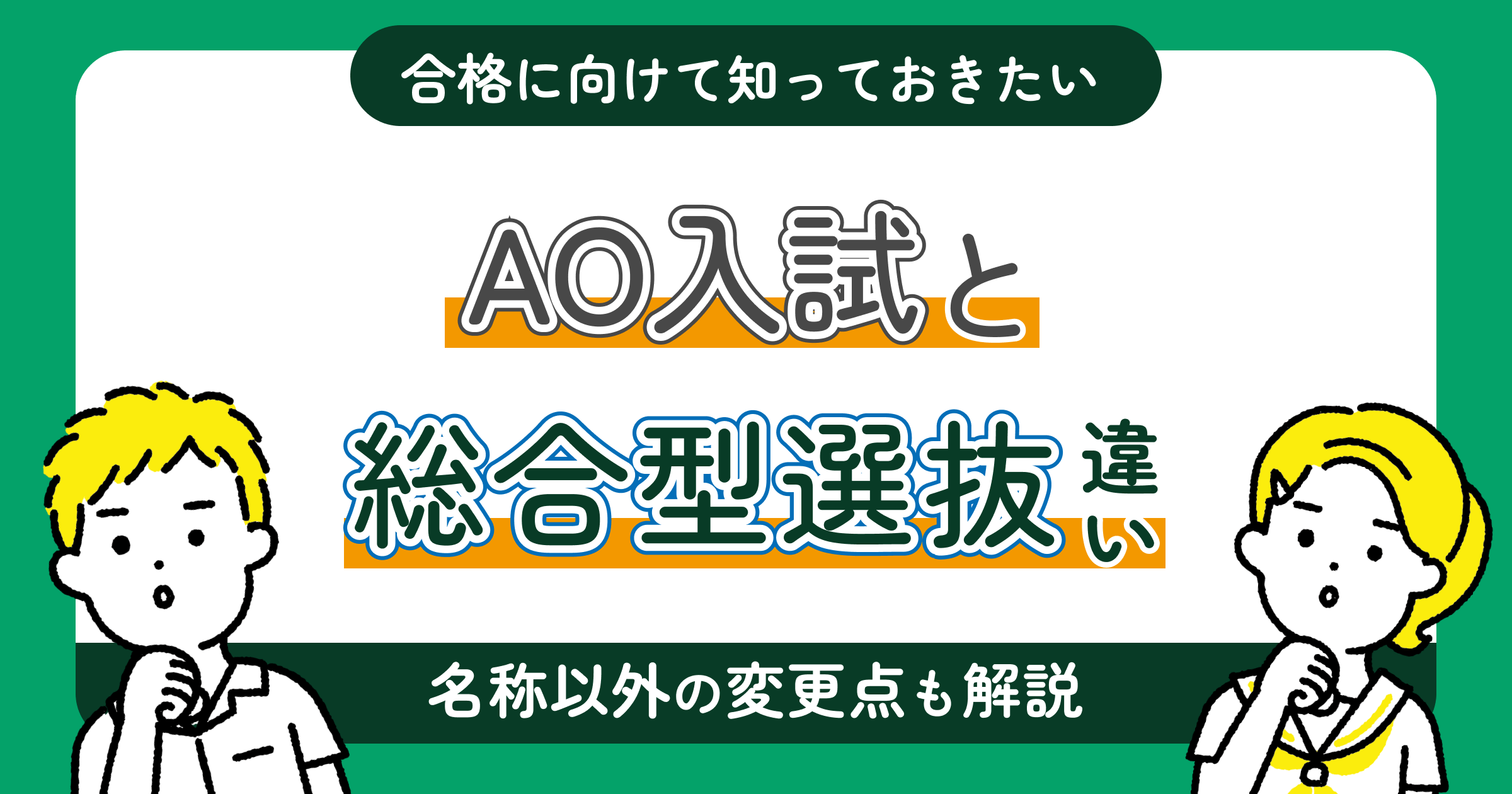
推薦入試は2つに大別されている
推薦入試は大きく「学校推薦型選抜」と「総合型選抜」の2種類に分けられます。
| 入試の種類 | 主な出願条件 | 主な評価観点 |
|---|---|---|
| 学校推薦型選抜 | 高校からの推薦を受けた人のみ出願可能 | 学業成績・校内評価などの実績重視 |
| 総合型選抜 | 本人の意思により出願可能 | 目標意識・将来のビジョンなどの意欲重視 |
学校推薦型選抜は、高校の推薦を受けて出願する方式です。評定平均や学校での活動実績などが選考の基準となります。一方で、総合型選抜は本人の入学意欲があれば出願できる入試方式です。自己推薦書や面接、小論文などを通じて多面的に評価され、合否を判定されます。
学校推薦型選抜が高校での学業成績や校内評価を重視するのに対し、総合型選抜は受験生の目標意識や将来へのビジョンを評価の中心としているのが大きな違いです。どちらも学力試験だけでは測れない力を評価するという点では共通していますが、出願の仕組みや評価軸は明確に異なります。
自分の強みがどちらの方式により適しているかを理解し、チャレンジすることが大切です。
総合型選抜と学校推薦型選抜の特徴をそれぞれ詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。


一般入試との違い
総合型選抜や学校推薦型選抜と、一般入試との最大の違いは評価されるポイントにあります。
上述したように、推薦入試や総合型選抜では個性や意欲、学習過程などを含めて合否を判定します。一方で一般入試では学力試験の得点が主な基準となります。
また、実施時期においても両者には明確に違いがあります。一般入試の試験日は年始から実施されるのに対し、学校推薦型選抜や総合型選抜は秋頃から選考が始まるのが特徴です。そのため、推薦入試の方が早めに進路を決定できるというメリットもあります。
評価軸から実施時期まで違いが多くある入試方式なので、自分に合ったものを選択して受験戦略を練ることが重要です。
AO入試と他の推薦入試は何が違う?
AO入試と他の推薦入試の違いは、出願の条件と評価基準にあります。
学校推薦型選抜(指定校推薦・公募推薦)が高校からの推薦を前提とするのに対し、AO入試(総合型選抜)は受験生本人の意思で出願できます。また、AO入試では人物像や将来性が重視されるのに対し、学校推薦型選抜では高校での成績や活動実績が評価の中心です。
ここからは次のトピック別に、AO入試と他の推薦入試における違いを詳しく解説します。
試験内容の違い
AO入試(総合型選抜)と学校推薦型選抜では評価する観点が異なるため、試験でアピールすべき内容にも違いがあります。
| 入試方式 | 試験内容 |
|---|---|
| AO入試(総合型選抜) | 自分の能力・経験をアピールする試験 |
| 学校推薦型選抜 | 過去の実績やこれまでの経験を中心にアピールする試験 |
AO入試では、面接・プレゼンテーション・小論文・活動報告書などさまざまな試験内容が存在しています。受験生の意欲や思考力、主体性を総合的に判断しているのが特徴です。
一方で学校推薦型選抜は、調査書・評定平均・面接・小論文などが主な試験内容です。学力検査は実施していないものの、高校在学中の学業成績を中心に評価する傾向があります。
AO入試は受験生の将来像や学びへの熱意を重視し、学校推薦型選抜は高校での努力が評価軸です。志望校合格のためにも、自分の強みが活かせる判断軸で評価される入試方式を選択しましょう。
出願条件の違い
AO入試(総合型選抜)と学校推薦型選抜では、出願においても本人の意思によるものと学校の推薦が必要なもので異なります。
| 入試方法 | 出願条件 |
|---|---|
| AO入試(総合型選抜) | 本人の意思次第で出願できる |
| 学校推薦型選抜 | 学校の推薦があれば出願できる |
AO入試は基本的に誰でも出願可能です。高校の推薦書が不要な場合が多く、一般的には成績基準も設けられていません。そのため、部活動やボランティア、探究活動などで自分を表現できる人に適しているといえます。
一方、学校推薦型選抜では学校長の推薦が必要です。また、指定校推薦のおいては学校ごとに出願できる人数に上限が設けられています。公募推薦に関しても大学ごとに一定以上の評定平均値や欠席日数などの条件を満たすことが必要です。
AO入試は自らの意思で挑戦でき、学校推薦型選抜は高校からの推薦を受けて挑戦できるという違いがあります。
受験可能な大学の違い
AO入試(総合型選抜)は学校推薦型選抜よりも限られた大学で実施されているため、事前に調べておくことが重要です。
| 入試方式 | 入試を実施している大学 |
|---|---|
| AO入試(総合型選抜) | 学力以外の能力を重視する方針を出している大学でのみ実施 |
| 学校推薦型選抜 | 国公立から私立まで幅広い大学で実施 |
AO入試は、個性や探究活動を重視する大学や明確な教育理念を持つ学部で多く行われています。一方、学校推薦型選抜は大学の特色に関わらず私立大学から国公立大学まで幅広く実施されているのが特徴です。国立大学の中には、推薦型選抜を主要な入試手段の一つとして位置づけているところもあります。
大学の入試方針によりAO入試を実施していない大学・学部・学科もまだ多く存在しています。志望大学の入試方式は事前にしっかりと確認しておきましょう。
難易度・落ちる確率の違い
AO入試(総合型選抜)と学校推薦型選抜などの他の入試方式と比較すると、難易度や落ちる確率はAO入試の方が高い傾向にあります。
たとえば青山学院大学文学部の入試では次のような倍率の結果が出ています。
【2025年度青山学院大学文学部 入試結果】
| 入試方式 | 倍率 |
|---|---|
| 自己推薦/AO入試(総合型選抜) | 約4.0倍前後 |
| 学校推薦型選抜 | 1.0倍 |
「学校推薦型選抜」方式の倍率は1.0倍なのに対し、「自己推薦/総合型選抜(旧AO入試)」では約4.0倍前後という高い倍率が出ています。
学校推薦型選抜は出願条件を満たした学生のみが対象になるため、そもそもの競争が抑えられています。一方AO入試では意志があれば出願できるため志願者数が多く、必然的に倍率も3倍~4倍以上となるケースが多いのです。
AO入試は出願の難易度が低い分、学校推薦型選抜と比較すると落ちる確率が高い入試方式であるといえます。
上記を踏まえ、総合型選抜と学校推薦型選抜の違いを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。
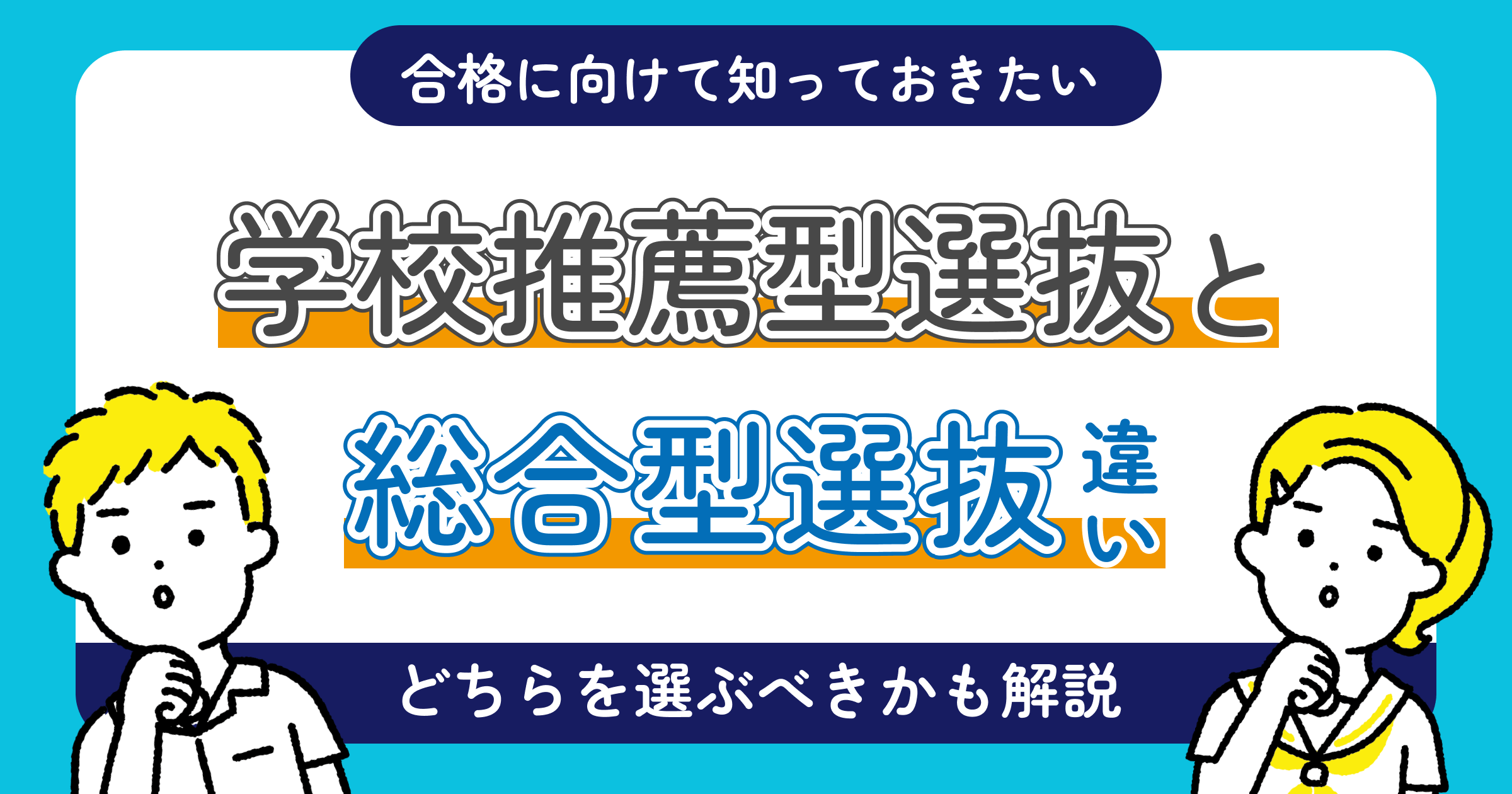
AO入試・推薦入試は受けるべき?
AO入試や推薦入試は個性やこれまでの経験などのアピールポイントが多い人におすすめの入試方式です。
志望校への入学に対して熱意のある人は、合格できる可能性が高いといえます。一般入試だけで合格を目指すよりも入学のチャンスを増やすことができるので、受けることで得られるメリットは大きいです。
ここからはそれぞれに向いている人の特徴を紹介します。
AO入試はこんな人におすすめ
AO入試(総合型選抜)は、自分の経験や考えを言葉で表現するのが得意な人、目標意識が明確な人に向いています。たとえば、部活動やボランティア、探究活動などで得た経験を通して「なぜその大学で学びたいのか」を具体的に語れる人は有利です。
また、入試時期が早いため、早く進路を決めたい人にも適しています。ただし、志望理由書や面接対策などを丁寧に行う必要があるため準備には時間がかかります。
そのため、自分の考えを整理し、大学の求める人物像と重ねて考えられる人にはおすすめできる入試です。学力だけでなく行動力や表現力で勝負したい人にとって、AO入試は大きなチャンスとなります。
総合型選抜の特徴についてより詳しく知りたい人は、以下の記事でも紹介しているので参考してください。

学校推薦型選抜はこんな人におすすめ
学校推薦型選抜は、コツコツと努力を重ねてきた人や、学校生活での実績を持つ人に適しています。
評定平均が安定して高く、欠席が少ない人は特に有利です。また、部活動や委員会活動などで学校に貢献してきた経験も評価されやすく、日頃の取り組みが結果につながる入試といえます。
出願条件が明確な分、AO入試よりも「確実に準備できる安心感」がある入試といえます。地道な努力を積み重ねてきた人、安定した成績を強みにしたい人におすすめです。
AO入試・推薦入試を受ける際によく抱く疑問
最後に、AO入試や推薦入試を受ける際によく抱く疑問へまとめて回答します。
AO入試と一般入試はどっちが難しい?
次のように、AO入試と一般入試では合否を判断する基準が異なります。
| 入試方式 | 判断基準 |
|---|---|
| AO入試 | 大学が求める人物像との合致しているか |
| 一般入試 | 学力試験の結果が基準を超えているか |
一般入試は学力試験が判断基準となるため、当日の点数のみが合否を左右します。一方、AO入試は人物評価を重視するため、知識だけでなく考え方や表現力が問われます。このように、そもそもの性質に違いがあるためどちらの方が難易度が高いかは人により異なります。
AO入試においては、学力に自信があっても自己分析や志望理由が曖昧だと合格は難しいでしょう。逆に、学力が平均的でも、自分の目標を明確に語れれば合格の可能性が高まります。
一般入試は「得点力」、AO入試は「自己理解と発信力」の勝負です。どちらが難しいかではなく、自分の強みをより発揮できるのがどちらかを基準に選ぶことが大切です。
AO入試と推薦入試は両方受けられる?
AO入試(総合型選抜)と推薦入試の一つである学校推薦型選抜の両方を受けることは可能です。
ただし、出願時期が重なる場合があるためスケジュール管理には注意が必要です。AO入試は夏から秋にかけて出願が始まり、学校推薦型選抜は秋以降が中心となります。
たとえばAO入試で不合格となった場合、推薦や一般入試に切り替えて再挑戦するケースもよく見られるものです。ただし、推薦の場合には高校によっては出願人数に制限が設けられている可能性があります。受験戦略を練る際に、あらかじめ進路指導の先生と相談しておくことが大切です。
まとめ
この記事では、推薦入試やAO入試の特徴とその違いについて解説しました。
AO入試(総合型選抜)や学校推薦型選抜などの推薦入試は、いずれも学力試験だけでは測れない力を評価する入試方式です。AO入試は主体性や将来の目標を重視し、学校推薦型選抜は高校での実績や信頼を評価しています。
どちらも早期の準備が欠かせず、志望理由書や面接を通じて自分の考えを明確に伝える力が重要です。自分の強みを活かせる入試を見極めたうえで、合格に向けた受験対策を進めていきましょう。